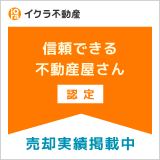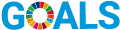Blog
ブログ
2025.09.22
遺品整理の最適な時期はいつ?後悔しないための3つのタイミングをご紹介!
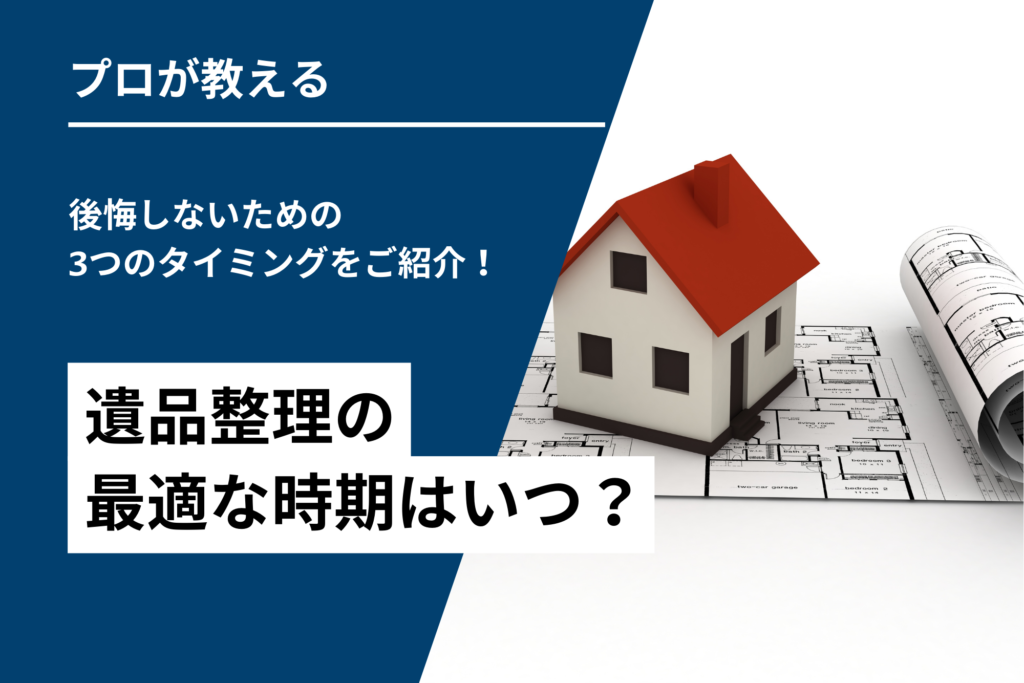
大切な方を亡くし、悲しみの中で「遺品整理はいつから始めれば良いのだろう」と悩んでいませんか?故人の持ち物と向き合うのは精神的な負担も大きく、何から手をつけて良いか分からない方も多いでしょう。
特に、相続や不動産売却といった手続きが絡むと、より複雑に感じてしまうものです。本記事では、遺品整理を始めるタイミングの目安から、後悔しないための具体的な注意点、スムーズに進める方法まで解説します。

遺品整理の時期はいつからはじめるべき?

遺品整理を行うタイミングに、法律上の明確な決まりはありません。しかし、遺品整理を始める時期は、葬儀や各種手続きのスケジュール、故人や遺族の状況によって最適なタイミングが異なります。
悲しみの中、無理に遺品整理を進める必要はありませんが、期限のある手続きに間に合わせるためにも、ある程度の目安を把握しておくことが大切です。
遺品整理を始めるおすすめのタイミングは3つ

遺品整理を始める時期に正解はありませんが、故人との関係性や遺品の状況によって、適したタイミングが存在します。ここでは、遺品整理を始めるのにおすすめの3つのタイミングと、メリット・デメリットについて詳しく紹介します。
1.葬儀後から四十九日法要まで
葬儀が終わった直後から四十九日法要までの期間は、遺品整理を始める時期として最も早いタイミングです。特に故人が賃貸物件に住んでいた場合など、早急な対応が求められるケースに適しています。
この時期は親族が集まりやすいタイミングでもあるため、故人の遺産や形見分けについて話し合う場を設けやすいのがメリットです。
一方、故人を亡くしたばかりで精神的に落ち着いていない中、多忙な手続きと並行して遺品整理を行う必要があるため、身体的・精神的な負担が大きくなるというデメリットもあります。また、相続に関する重要な書類などを誤って処分してしまわないよう、慎重な作業が必要です。
2.四十九日法要後
四十九日の法要を終えた後は、遺品整理を始めるタイミングとして最も一般的です。四十九日をもって忌明けとなり、遺族の気持ちにもある程度の区切りがつくため、故人の持ち物と向き合う準備が整いやすい時期と言えます。
また、葬儀直後に比べて時間に余裕があり、賃貸物件の契約更新や相続放棄の期限などを意識しながら、落ち着いて作業を進められます。この時期に遺品整理を行うと、親族間のトラブルを防ぎつつ、故人の遺品を丁寧に整理できるでしょう。
ただし、故人が遺した遺品が多すぎる場合や、遠方に住んでいて頻繁に足を運べない方は、一人で全てを片付けるのは困難な可能性があります。
3.相続税の申告期限前
故人が亡くなってから10ヶ月以内と定められている相続税の申告期限前も、遺品整理を始める重要なタイミングの一つです。特に、故人の準確定申告(故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を確定申告する)や、相続する財産に不動産や高額な物品が含まれる場合は、正確な財産調査が欠かせません。
遺品整理をすると、現金や預金通帳、有価証券、貴金属類、不動産の権利書など、相続財産を特定しやすくなります。期限ギリギリで慌てないよう、故人の死亡後7〜8ヶ月を目安に遺品整理を済ませておくとよいでしょう。
このタイミングを逃すと、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。
なお、家を相続した場合にかかる税金については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:家(不動産)を相続した場合にかかる税金とは?必要な手続きや相続税の計算方法をご紹介! | ビリーフ株式会社
遺品整理の具体的な方法は2つ

遺品整理の具体的な方法について解説します。それぞれの詳しい内容について見ていきましょう。
1.自分で行う
自分たちで遺品整理を行う場合、まずは親族で集まり、遺品の分け方や処分の仕方について話し合うのが大切です。次に、作業を分担し貴重品や現金、重要な書類から先に探し出しましょう。
その後、衣類や書籍など、大型の遺品を整理していきます。この際、自治体のゴミ分別ルールを事前に確認し、適切な方法で処分するのが重要です。
また、形見分けをしたい場合は、親族間で十分に話し合い、誰に何を渡すか決めておくと、後々のトラブルを防げます。
2.業者へ依頼する
遺品の量が多かったり、遠方に住んでいて作業が難しかったりする場合、遺品整理業者への依頼も有効です。遺品整理業者は、遺品の分別から処分、清掃までを専門的に行ってくれるため、遺族の身体的・精神的負担を大幅に軽減できます。
業者に依頼する際は、複数の業者から相見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討するのがおすすめです。また、作業内容や追加料金の有無についてもしっかりと確認してから契約を結びましょう。
遺品整理で後悔しないための注意点は4つ

遺品整理は、故人を偲び、遺品を通じて思い出を整理する大切な時間です。予期せぬトラブルや後悔につながるような事態を避けるために、事前に注意すべきポイントを把握しておきましょう。
1.親族間で勝手に遺品整理を進めない
遺品整理は、故人の遺産を巡る相続トラブルに発展する可能性があるため、親族間で勝手に遺品整理を進めるのは避けるべきです。特に、現金や貴金属、骨董品など金銭的価値のあるものは、相続財産と見なされるため、必ず相続人全員の合意を得てから整理に取り掛かりましょう。
遺言書やエンディングノートが残されている場合は、まず内容を確認し、故人の意思を尊重した上で作業を進めることが重要です。もし遺品整理の過程で意見が対立した場合は、無理に進めず、弁護士などの第三者への相談も検討しましょう。
2.遺品を分類しておく
遺品整理の第一歩は「必要」「不要」「保留」の分類です。「必要」なものは、故人の思い出の品や形見分け、重要な書類、相続財産などです。
「不要」なものは、故人が生前に処分を望んでいたものや、明らかにゴミと判断できるもの「保留」は、判断に迷うものや、親族の意見を聞く必要があるものになります。分類作業は、故人の思いを尊重しながら、無理のない範囲で進めましょう。
一度にすべてを片付けようとせず、焦らずじっくりと時間をかけると、後悔のない遺品整理になります。
3.期日が決まっている書類がないか確認する
遺品整理の際、故人が遺した書類の中に、期限付きの手続きが必要なものが含まれている場合があります。例えば、公共料金やクレジットカードの支払い明細、年金関連の書類など、解約手続きや名義変更が必要な書類がないかを確認しましょう。
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、賃貸契約の解約手続きを早急に行う必要があります。これらの手続きを怠ると、予期せぬ支払いが発生したり、トラブルに発展したりする可能性があるため、遺品整理の初期段階で必ず確認してください。
なお、不動産の名義変更費用が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:不動産の名義変更費用はいくら?内訳と相場、安く抑える3つの方法をご紹介! | ビリーフ株式会社
4.遺品整理業者選びは慎重に行う
遺品整理を専門業者に依頼する場合、業者選びを慎重に行うのが大切です。遺品整理業界には、悪質な業者も存在するため、料金体系が明確か、必要な許可(古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可など)を保有しているか、実績が豊富かなどを事前に確認しましょう。
複数の業者から相見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討すると、安心して任せられる業者を見つけられます。また、見積もりの際に、追加料金が発生する可能性についてもしっかり確認しておくと、後々のトラブルを防げるでしょう。
遺品整理 時期でよくある3つの質問
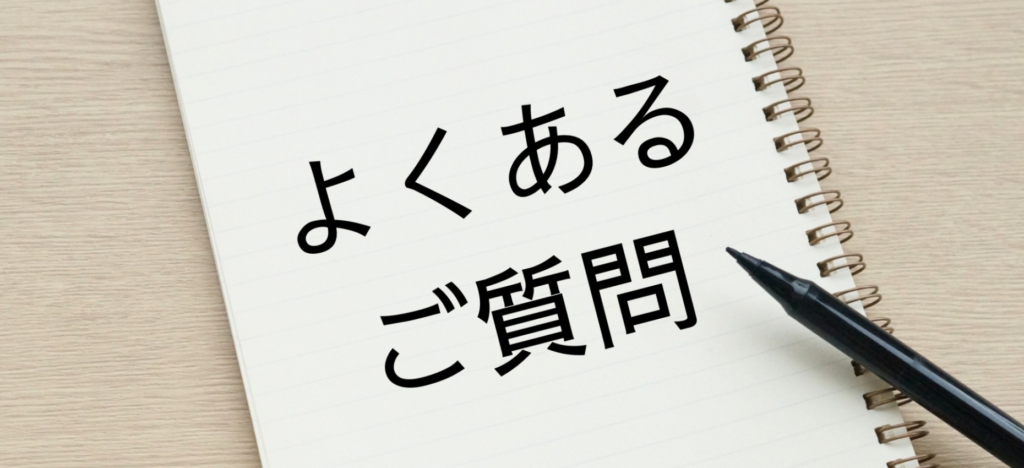
遺品整理の時期についてよくある質問を3つご紹介します。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
質問1.遺品整理は1人でやるべきですか?
遺品整理は、故人の思い出が詰まった品々と向き合う作業です。精神的な負担が大きいため、一人で行うのではなく、可能な範囲で親族や友人に協力してもらうのをおすすめします。
親族が集まって遺品を整理すると、故人を偲ぶ機会にもなりますし、大切な書類や品物を誤って処分してしまうリスクを減らせます。
遠方に住んでいる場合や、親族の都合が合わない場合は、無理に一人で抱え込まず、遺品整理専門業者への依頼も検討しましょう。専門家は効率的に作業を進めてくれるため、短期間で整理を完了させられます。
質問2.遺品整理と相続には関係がありますか?
遺品整理と相続は密接に関係しています。遺品整理をすると、故人の現金や預金通帳、株式、不動産関連の書類など、相続財産を正確に把握できるでしょう。特に、相続税の申告には故人の財産をすべて洗い出す必要があるため、遺品整理が非常に重要な作業となります。
遺品整理の過程で発見された遺言書やエンディングノートは、相続手続きにおいて重要な意味を持ちます。遺産分割を円滑に進めるためにも、まずは遺品を丁寧に確認し、何が相続財産となるのかを把握するのが大切です。
質問3.遺品整理を先延ばしにするとどうなりますか?
遺品整理を先延ばしにすると、さまざまな問題が発生する可能性があります。まず、故人が賃貸物件に住んでいた場合、不要な家賃や管理費を支払い続けなければなりません。
また、遺品の中に重要な書類や相続財産が埋もれていると、手続きの遅れや相続トラブルの原因となる場合もあります。
さらに、時間の経過とともに遺品が劣化したり、カビや害虫が発生したりする可能性もあります。精神的な負担を軽減するためにも、体調や気持ちと相談しながら、少しずつでも計画的に進めていくのが大切です。
まとめ
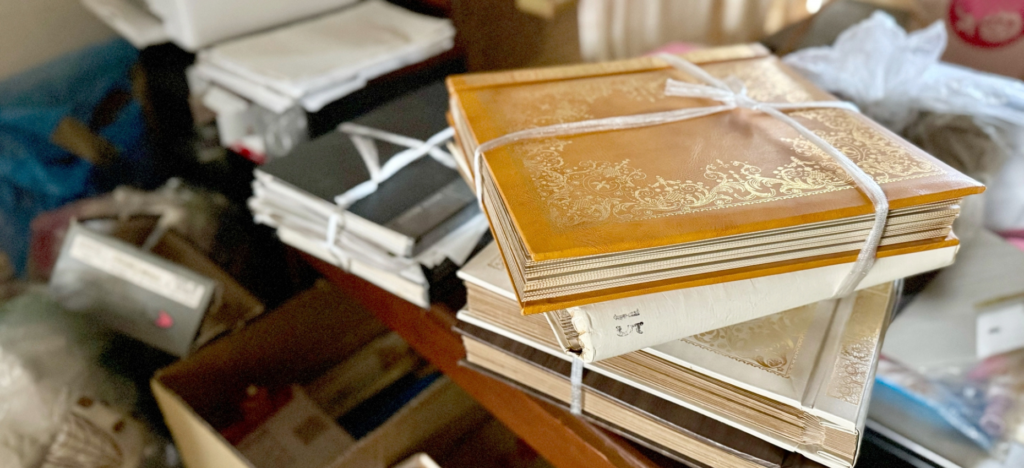
遺品整理を始める時期に明確な決まりはありませんが、葬儀後、四十九日法要後、相続税の申告期限前の3つのタイミングが、遺族にとって区切りをつけやすい目安です。特に、故人が賃貸物件に住んでいた場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、各種手続きの期限を考慮して計画的に進める必要があります。
また、後悔しない遺品整理を行うためには、親族間で十分に話し合い、協力してた取り組みが不可欠です。必要に応じて、遺品整理業者や司法書士、税理士などの専門家のサポートも活用し、遺品整理を進めていきましょう。