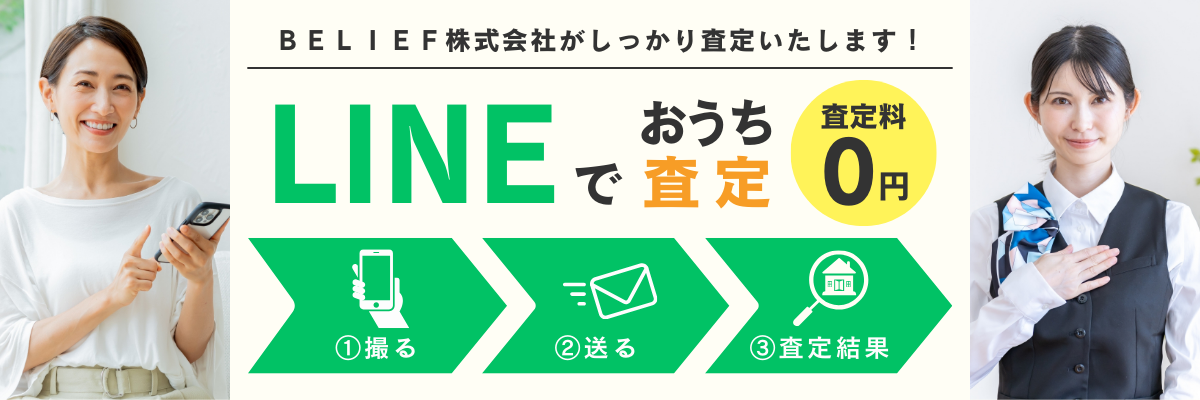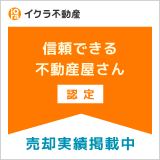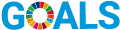Blog
ブログ
2024.12.23
共有名義不動産の売却方法とは?必要な書類や共有持分買取業者に売却するリスクを徹底解説!
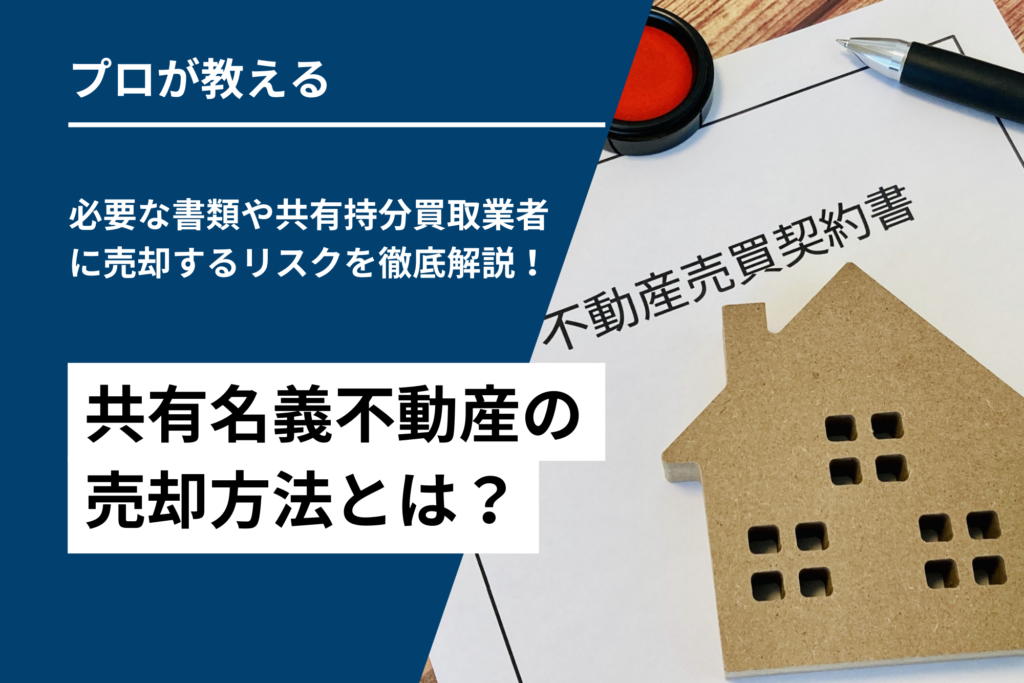
共有名義の不動産を売却する際に、「手続きが複雑そう」「トラブルが心配」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。共有名義の不動産は、独自名義とは異なる複雑な手続きや注意点が多く、適切な方法を知らないとトラブルにつながりかねません。
本記事では、共有名義不動産の売却方法や必要な書類、共有持分買取業者に売却するリスクをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

共有名義の不動産とは?

不動産の「共有」とは、複数人での土地や建物などの共同所有を指し、これらは「共有名義の不動産」と呼ばれます。共有者にはそれぞれの持分が割り当てられ、権利を「共有持分」と言います。
不動産は現金のように分割が容易ではないため、相続時に兄弟で共有名義にしたり、夫婦や親子で住宅を共同名義にしたりするケースが多いです。
共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できないため、意見の相違が生じるとトラブルに発展する可能性があります。このため、共有名義の運用には慎重な合意形成が求められます。
共有者の権利と同意の範囲
不動産を複数人で共有する場合、それぞれの共有者には行える行為が法的に制限されています。物件の保存行為や個人での使用は、ほかの共有者の同意がなくても実施できますが、使用に際してはほかの共有者への使用料が発生する場合があります。
一方で、物件の管理や改良を目的とした行為には、共有持分の過半数の同意が必要です。たとえば、短期賃貸契約の締結や建物のリフォームなどが該当します。
さらに、物件の売却や権利変更といった処分行為には、共有者全員の同意が不可欠です。このようなルールにより、共有名義の不動産をめぐる合意形成には十分な配慮が求められます。
共有持分であれば自由に売却できる
共有名義の不動産において、共有者は不動産全体を自由に売却できませんが、自身が持つ「共有持分」については例外です。共有持分は、それぞれの共有者に与えられた独立した権利であり、ほかの共有者の許可や通知なしに自由に売却が可能です。
たとえば、複数人で土地を共有している場合、そのなかの1人が持つ共有持分のみを第三者に譲渡できます。この仕組みは、共有者が不動産全体ではなく、自分の権利範囲内で意思決定を行えるよう保障されたものです。
しかし、共有持分の売却は新たな共有者との関係性や意見の相違を生む可能性があるため、慎重な判断が求められる場合があります。
共有名義不動産の売却方法

次は、共有名義不動産の売却方法について解説します。
- 共有者の同意を得て売却する方法
- 自分の持分のみを売却する方法
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
共有者の同意を得て売却する方法
共有名義の不動産を売却する際には、全員が合意して不動産全体を売却する方法が一般的です。この手法は、不動産全体を相場価格で売却できる点がメリットです。売却代金は共有持分の割合にもとづいて分配されるため、公平性も確保されます。
しかし、共有者が多い場合や意見が一致しない場合には、手続きが煩雑になる可能性があります。また、売却手続きでは共有者全員の署名と捺印が必要なため、事前の準備が欠かせません。
共有者の一部が売却に反対する場合には、リースバックの活用も検討が可能です。この方法では、不動産を一度売却して現金化しながら、その後も家賃を支払って同じ物件に住み続けられます。
自分の持分のみを売却する方法
共有名義の不動産において、自分の共有持分だけを売却することは可能ですが、いくつかの注意点があります。たとえば、ほかの共有者の許可は不要ですが、土地や建物の物理的な分割が難しいため、共有持分のみを購入する人は少ないのが実情です。
このため、共有持分買取業者に売却する方法が選ばれる場合があります。共有持分買取業者を利用すると、売却がスムーズに進むというメリットがありますが、一般的な不動産取引と比べて売却価格が低くなる傾向があります。
また、土地の場合は分筆して単独名義にし、共有状態を解消してから売却するのも1つの方法です。しかし、分筆には測量や登記の手続きが必要で、時間と費用がかかる点を踏まえて進めなければなりません。
共有名義不動産の売却に必要な書類

共有名義不動産の売却に必要な書類は、以下のとおりです。
- 「登記識別情報」または「登記済権利証」
不動産の登記時に発行されるもので、時期によって形式が異なる。共有名義の場合、登記識別情報は共有者それぞれに発行されるのが一般的
- 「土地測量図」や「境界確認書」
この書類がない場合、測量を依頼し境界を確定する必要がある
- 「実印」「印鑑証明書」「住民票」
それぞれの書類を全員分揃える必要がある
手続きが複雑なため、不動産会社や司法書士のサポートを受けるとスムーズに進められます。
共有持分買取業者に売却するリスクは3つ

次は、共有持分買取業者に売却するリスクについて解説します。
- 持分の売却・買取の交渉が発生する
- 共有不動産購入者に出入りされる
- 家賃請求や税金滞納のリスクがある
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.持分の売却・買取の交渉が発生する
買取業者は購入後、ほかの共有者に対してその持分の売却や買い取りを持ちかけるのが一般的です。これにより、ほかの共有者がプレッシャーを感じたり、予期しない取引を強要されたりする可能性があります。
一方で、共有者同士で話し合い、自分の持分をほかの共有者に売却すれば、このようなリスクを回避できます。さらに、自分がほかの共有者の持分を買い取って、完全な所有権を得るのも1つの方法です。
どちらの場合でも、金額については十分な交渉が欠かせません。納得できない条件では妥協せず、不動産専門家に相談するのがおすすめです。
2.共有不動産購入者に出入りされる
共有名義の不動産が第三者に売却されると、購入者には物件への立ち入りや使用の権利が発生します。この結果、購入者が実際に物件を利用しはじめる場合もあるため、元の共有者にとってストレスの原因になりかねません。購入者とのやり取りや、物件使用に関する料金請求は精神的な負担となる可能性があります。
このような状況を避けるため、売却前にほかの共有者間で話し合い、第三者ではなく既存の共有者に持分を譲渡する選択肢を検討しましょう。また、事前に不動産専門家に相談して、円滑に手続きを進める方法を模索するのもおすすめです。
3.家賃請求や税金滞納のリスクがある
共有名義の物件を貸し出している場合、毎月の家賃収入は共有持分割合に応じて各共有者に分配されます。しかし、共有持分が第三者に売却されると、新たな所有者からその持分にもとづいた家賃の請求が行われる可能性があります。
また、物件にかかる固定資産税も持分割合に応じて、それぞれの共有者が負担する義務があるため、持分売却後には新しい共有者と税金の分担について話し合わなければなりません。この過程で意見の対立が生じると、税金の支払いが滞り、結果的にリスクが高まる可能性があります。
このような問題を避けるため、事前に共有者間での合意形成や分担の確認を行い、スムーズな売却や管理が進められるよう準備しましょう。
なお、不動産売却で起こりがちなトラブルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:不動産売却で起こりがちなトラブルとは?回避するための事前対策も紹介!
許可なく共有持分を売却された場合の対処法

許可なく共有持分を売却された場合の対処法は、以下のとおりです。
- 売却された共有特分を買い取る
不動産を引き続き所有したい場合は、売却された持分を自分で買い取り、単独所有にする。この際、事前に市場価格を調べ、不利な条件で購入しないよう準備しておく必要がある
- 自分の共有特分を売却する
物件を維持するのに特別なこだわりがない場合、自分の持分を売却して、現金化すれば、有効活用できる
- 現状を維持する
共有状態を続ける方法も考えられるが、第三者との間で新たなトラブルが発生するリスクが伴う
どの方法にするとしても、専門家に相談しながら進めると、最適な解決策を見つけられます。
共有不動産の売却でよくある3つの質問
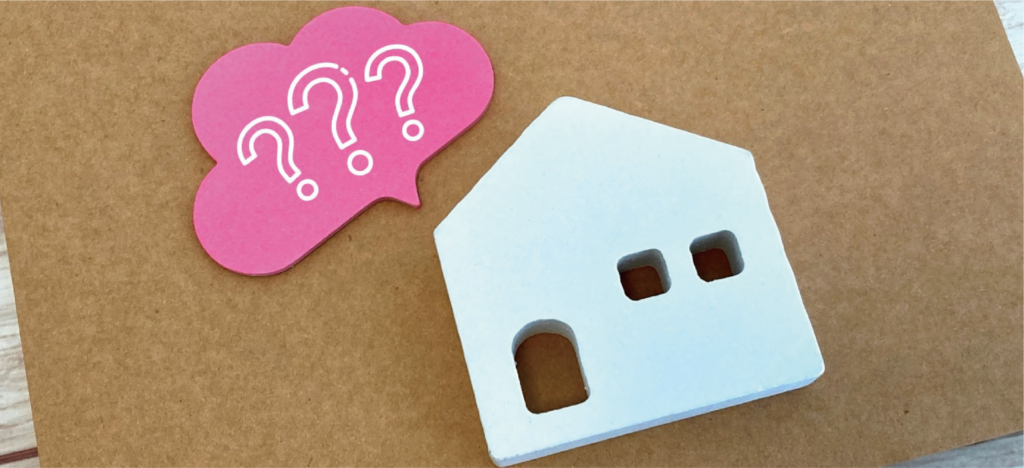
次は、共有不動産の売却でよくある質問について紹介します。
- 質問1.不動産の共有を避ける方法は?
- 質問2.共有持分の売却にかかる費用は?
- 質問3.共有名義の不動産を売却する際の流れは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.不動産の共有を避ける方法は?
不動産の共有トラブルを避けるためには、相続時から適切な対策を講じる必要があります。まず、遺産分割時に共有名義を避けることを検討しましょう。
不動産の分け方には、現物分割(土地を分筆して分ける)、代償分割(代償金を払って単独所有にする)、換価分割(売却して現金を分ける)の3種類があります。これらの方法を活用することで、共有による将来の問題を未然に防げます。
すでに共有名義となっている場合は、早めに共有状態を解消するのが理想的です。また、トラブルが発生した場合や解決方法に迷った際には、不動産分野に詳しい弁護士に相談すると、適切なアドバイスを得られます。
質問2.共有持分の売却にかかる費用は?
共有持分の売却にかかる費用は、以下のとおりです。
- 売買契約書に対する印紙税
契約金額に応じて課税され、通常5,000円~3万円程度が目安
- 登録免許税
売却に伴う登記手続きで、抵当権の抹消などが必要な場合、不動産1件につき1,000円の税金がかかる
- 司法書士報酬
抵当権抹消登記を依頼する場合、報酬として5,000円~1万円程度が相場
- 仲介手数料
不動産会社を通じて売却する場合、仲介手数料が発生する。この金額は売買価格によって異なり、売却金額が400万円を超える場合、(売買価格の3%+6万円)+消費税が上限となる
- 譲渡所得税に関する税
共有特分の売却において譲渡所得が発生する場合は、保有期間に応じた所得税と住民税などが課される。譲渡所得には、長期と短期に分かれ、それぞれ税率が異なる
質問3.共有名義の不動産を売却する際の流れは?
共有名義の不動産を売却する際の流れは、以下のとおりです。
- 共有者全員を明確に把握する
登記事項証明書を取得して、共有者の権利関係を正確に確認する。相続を繰り返している場合、予期せぬ共有者が存在する可能性もあるため注意が必要となる
- まとめ役を決める
共有者が多い場合は、意見をまとめる役を決めるとスムーズ。また、知識や経験のある不動産専門家に依頼すると、トラブルを未然に防げる
- 売却に伴う費用の負担割合を決める
仲介手数料や印紙税、測量費用などは、持分割合に応じて分担するのが一般的
これらの準備を怠ると、トラブルにつながる可能性があるため、共有者間で十分に協議しておきましょう。
まとめ

本記事では、共有名義不動産の売却方法や必要な書類、共有持分買取業者に売却するリスクをご紹介しました。
共有名義の不動産とは、複数の共有者がそれぞれの所有分を持つ不動産です。共有者は自分の所有分を自由に売却できますが、不動産全体を売却するには全員の同意が必要です。売却方法としては、共有者全員の合意を得て売却する方法と、自分の持ち分のみを売却する方法があります。
売却に必要な書類としては、「登記識別情報」または「登記済権利証」、「土地測量図」や「境界確認書」などが挙げられます。これらを準備して、適切な購入手続きを進めなければなりません。
また、共有持分買取業者への売却には、購入者との交渉や家賃請求、税金滞納、購入者には物件への立ち入りなど、さまざまなリスクが発生します。このため、売却された共有特分の買い取りや自分の共有特分の売却、現状維持などの対処方法を選ぶ必要があります。
なお、「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから