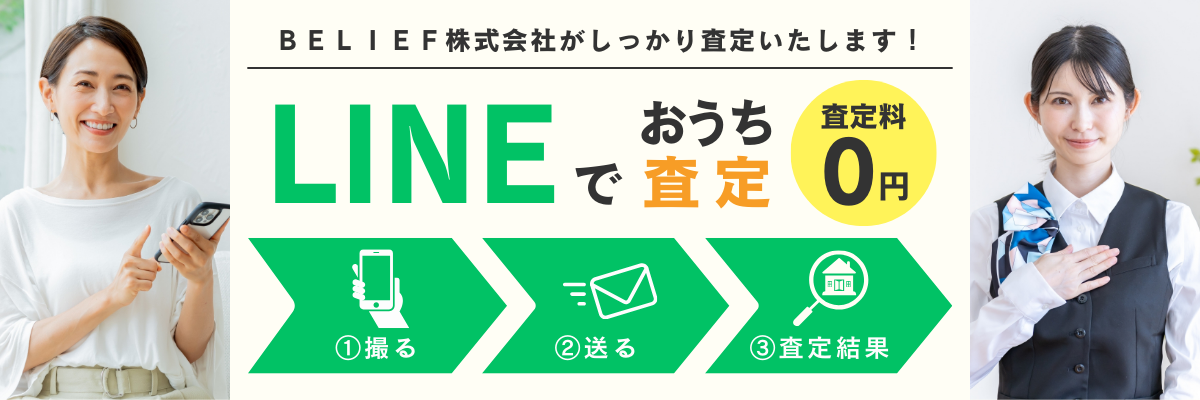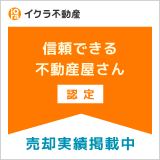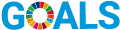Blog
ブログ
2025.03.14
家を貸すメリット・デメリットとは?家を貸す場合の契約方法や管理方法もご紹介します!

転勤や相続などで使わなくなった家を貸すべきか、悩まれている方もおられるのではないでしょうか。家を貸すと家賃収入が得られるため、魅力的な選択肢の1つですが、契約方法や管理方法など注意すべき点がいくつかあります。
本記事では、家を貸すメリット・デメリットや家を貸す場合の契約方法や管理方法をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

使わない家は貸すべき?

転勤や親との同居、相続によって所有者となった家を貸し出せば、家賃収入を得られて、将来的に再び住む可能性も残せます。しかし、賃貸にする際には入居者の募集や契約手続き、維持管理などの課題が伴います。
このため、安定した賃貸運営には、事前にリスクを把握して、適切な準備を進めなければなりません。
家を貸すメリットは3つ

次は、家を貸すメリットについて解説します。
- 家賃収入が得られる
- 家の所有権を持ち続けられる
- 家の劣化防止につながる
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.家賃収入が得られる
家賃収入は、生活費の補填や将来の備えとして活用でき、特に老後資金や教育資金の確保にも役立ちます。賃貸市場の需要が高いエリアであれば、安定した収入が見込めるため、不動産を活用した資産運用のひとつとして有効な手段となります。
しかし、空室リスクや維持費用などの課題もあるため、事前に十分な計画を立てなければなりません。
2.家の所有権を持ち続けられる
一時的に家を離れる場合でも、賃貸に出せば所有権を維持しながら活用できます。将来的に戻る可能性がある場合、契約の種類を慎重に選びましょう。
たとえば、期限を決めて貸し出したい場合は「定期借家契約」を結ぶと、契約満了後に確実に家を取り戻せます。一方、期間を限定せずに貸し出したい場合は「普通借家契約」が最適です。どの契約方法を選ぶかは、自分の今後の予定や賃貸の目的に応じて決めるようにしてください。
3.家の劣化防止につながる
家を長期間空き家のままにしておくと、湿気がこもりやすくなり、カビの発生や木材の劣化が進む場合があります。また、害虫や小動物が侵入しやすくなったり、配管が硬化したりなど、建物の老朽化を加速させる要因も増えてしまいかねません。
一方で、家を賃貸に出して誰かが住んでいる状態を維持すれば、換気や掃除が定期的に行われ、このような問題の発生を抑えられます。さらに、入居者が日常的に使用すると、設備の不具合にも早めに気づけるため、家の資産価値を維持しやすくなります。
家を貸すデメリットは3つ

次は、家を貸すデメリットについて解説します。
- 空室のリスクがある
- トラブルに発展する可能性もある
- 管理業務が発生する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.空室のリスクがある
家を賃貸に出しても、空室が続けば家賃収入は得られず、その間も固定資産税や維持管理費などの支出は発生し続けます。賃貸需要の低いエリアでは、借り手が見つかりにくく、想定した収益を得るのが難しくなる可能性があります。
空室リスクを抑えるためには、家賃や条件を市場に合わせて調整することが大切です。長期間入居者が決まらない場合は、不動産会社と相談して、より魅力的な募集条件を検討するようにしましょう。
2.トラブルに発展する可能性もある
家を貸し出す際には、入居者との間で家賃の滞納や騒音、設備の破損などのさまざまなトラブルが発生する可能性があります。このような問題を未然に防ぐためには、契約書に詳細な条件を記載して、借主と十分に確認を行うようにしましょう。
また、万が一トラブルが発生した際には、すみやかに対応できるよう、不動産会社や法律の専門家と連携しておくと安心です。事前に適切な対策を講じておくと、円滑な賃貸運営につながります。
3.管理業務が発生する
まず、所有者として固定資産税の支払い義務があり、加えて管理を専門会社に依頼する場合は管理委託費が必要です。また、入居者を募集する前に、物件のクリーニングやリフォーム、修繕を行うケースもあり、その費用負担を考慮しなければなりません。
さらに、入居後も設備の維持管理やトラブル対応が求められるため、長期的な視点で費用と手間を見積もってから賃貸経営を行うようにしましょう。
家を貸す場合の契約方法
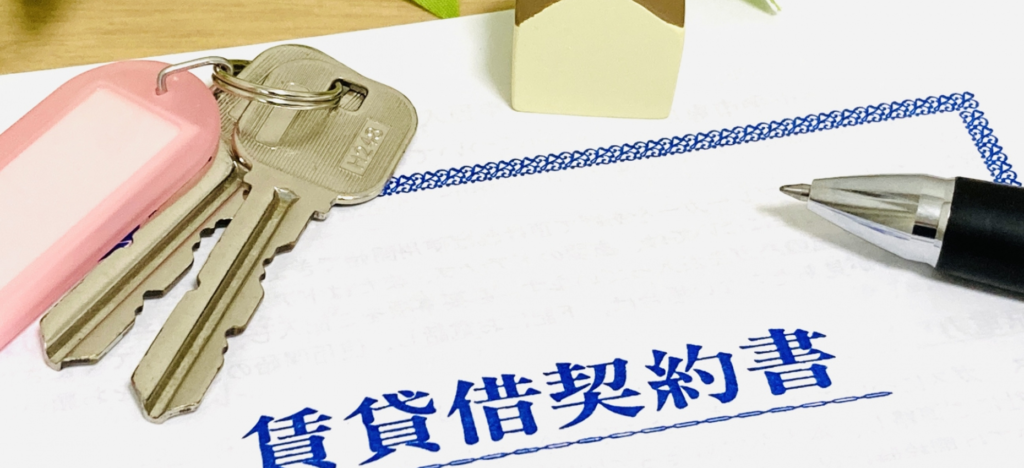
次は、家を貸す場合の契約方法について解説します。
- 普通借家契約
- 定期借家契約
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
普通借家契約
普通賃貸借契約では、契約期間は一般的に2年間とされ、契約満了後は借主が希望すれば自動的に更新される仕組みです。貸主にとってのメリットは、安定した家賃収入が得られますが、契約解除には正当な理由が必要となるため、貸主の都合のみの契約終了は困難です。
貸主が自身の住居として利用したい場合でも、正当事由が認められなければ退去を求められません。契約内容をよく理解して、将来的な計画も考慮したうえで賃貸運営を行うようにしましょう。
定期借家契約
定期借家契約は、貸主が契約期間を自由に決められる契約形態であり、契約更新がない点が特徴です。たとえば、一定期間の海外赴任や転勤が決まっている場合、その期間のみ家を貸したいときに適した契約となります。
契約満了時には、貸主の申し出により確実に物件を取り戻せるため、将来的に自身が住む予定がある場合にも安心です。しかし、長期間の居住を希望する借主には敬遠されやすく、契約期間が短いと入居者を見つけにくくなる可能性があります。
しかし、契約終了後、貸主と借主が合意すれば再契約も可能となります。
家を貸す場合の管理方法は3つ

次は、家を貸す場合の管理方法について解説します。
- 自主管理
- 管理委託
- サブリース
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.自主管理
自主管理とは、賃貸物件の管理をオーナー自身が行う方法です。管理会社に委託する必要がないため、管理費用を抑えられる点がメリットです。
また、オーナーが直接対応するため、修繕や入居者対応のスピードが速くなり、入居者の満足度が向上する可能性もあります。しかし、賃貸経営には入居者募集や契約手続き、家賃管理、メンテナンス対応など、幅広い業務が発生するため、時間と労力がかかる点がデメリットです。
このように、専門的な知識も必要となるため、状況に応じた管理方法の選択が大切です。
2.管理委託
管理委託は、賃貸物件の管理業務を不動産会社に依頼する方法で、日々の運営やトラブル対応を任せられます。遠方に物件を持つオーナーや、管理の負担を減らしたい人に適しており、手数料は一般的に賃料の5%程度です。
修繕対応や入居者対応など専門的な知識を要する業務を代行してもらえるため、安心して運用できる点がメリットです。しかし、管理委託には手数料がかかるため、収益に影響を与える可能性があります。
また、不動産会社によってサービスの質に差があるため、実績や対応力を十分に確認して、信頼できる会社を選ぶことが大切です。
3.サブリース
サブリースは、不動産会社がオーナーから物件を借り上げ、別の入居者に転貸する仕組みです。不動産会社が賃借人となるため、オーナーは安定した家賃収入を得やすくなります。手数料は賃料の約10%と高めですが、管理業務の負担を大きく軽減できる点が特徴です。
不動産会社が借り上げるため、実際の入居状況にかかわらず一定の家賃収入が保証されるケースが多いです。しかし、市場相場より家賃が低く設定される場合が一般的で、オーナーが受け取る収益が減る可能性があります。
さらに、礼金や更新料が不動産会社の収入となるため、手取りが少なくなる点に注意が必要です。
家を貸す際の流れ
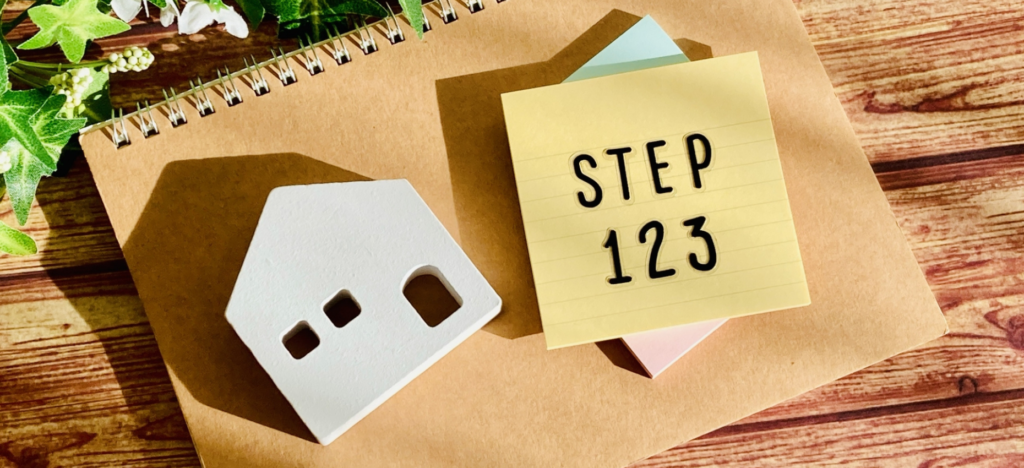
家を貸す際の流れは、以下のとおりです。
- 不動産会社への相談
不動産会社に相談して、家賃の設定や入居条件、管理方法などを決める。適切な条件を設定すると、スムーズに借り手を見つけられる
- 入居者募集・審査
条件が決まったら、入居者を募集する。物件の内覧を経て申し込みが入ったあと、入居者の支払い能力や信用情報を審査して、契約可否を判断する
- 賃貸借契約
入居者が決まれば、契約を締結する。不動産会社が仲介して、契約内容の説明や書類への署名・捺印を行う
- 更新・解約
普通借家契約では、契約更新を繰り返す。定期借家契約の場合、期間満了時に契約が終了するが、双方の合意があれば再契約が可能
不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

参考:ビリーフ株式会社
「ビリーフ」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。
さらに、不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、実務経験を活かして信頼性の高いアドバイスを提供しています。
家を貸す デメリットでよくある3つの質問

最後に、家を貸す デメリットでよくある質問について紹介します。
- 質問1.家を貸す際に知っておくべきポイントは?
- 質問2.家を貸す際の管理会社の選び方は?
- 質問3.賃貸か売却か判断する基準は?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.家を貸す際に知っておくべきポイントは?
家を貸す際に知っておくべきポイントは、以下のとおりです。
- 契約形態の選択
賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があり、貸主の意向に応じた選択が大切。たとえば、将来的に物件を自身で利用する予定がある場合、契約期間を定めた定期賃貸借契約が適している
- 信頼できる不動産会社の活用
賃貸管理には専門知識が必要であり、はじめて運営する場合は、信頼できる不動産会社のサポートを受けるのがおすすめ。サポート内容や実績を確認して、安心して管理を任せられる会社選びが大切
- 適正な家賃設定
物件の立地や設備、市場の相場を考慮しながら、適正な家賃を設定する必要がある。高すぎると入居者が見つかりにくく、低すぎると収益が減るため、事前の市場調査が大切
- 入居者の慎重な選定
家賃の滞納やトラブルを避けるため、入居者の信用情報や勤務先の確認を行い、慎重に審査をする。家賃保証会社を活用すると、リスクを軽減できる
- 物件の清潔さと魅力の維持
物件を貸し出す際は、清掃や修繕を行い、魅力的な状態を保つのが大切。ハウスクリーニングや設備の更新を検討して、良質な入居者を引きつける工夫を行う
質問2.家を貸す際の管理会社の選び方は?
賃貸管理会社を選ぶ際は、提供されるサービスの内容をよく確認しましょう。手数料の安さだけで判断すると、自分で対応しなければならない業務が増え、負担が大きくなる場合があります。
賃貸管理には、入居者対応や修繕手配、家賃管理など多くの業務があるため、複数の会社のサービスを比較して、自分にとって必要なサポートが充実している会社を選びましょう。
また、家を貸す目的によって適した管理会社は異なります。たとえば、転勤で一時的に家を貸す場合は、再入居を前提としたリロケーションの経験が豊富な会社を選ぶと安心です。
管理を一任できる「転貸」方式を採用している会社なら、煩雑な手続きを任せられるため、スムーズな運用が期待できます。
質問3.賃貸か売却か判断する基準は?
賃貸か売却か判断する基準は、以下のとおりです。
- 賃貸に出す場合
賃貸として活用する場合、毎月の家賃収入が住宅ローン返済額や維持費を上回るのが望ましい。管理会社への委託費や修繕費などのコストを考慮して、収支がマイナスになる場合、長期的な賃貸運営は難しくなる可能性がある
- 売却する場合
売却価格がローン残債を下回ると、自己資金で不足分を補う必要がある。売却を考えている場合は、不動産市場の相場を調べて、適切な価格で売れるかを確認することが大切
どちらの方法を選択したとしても、信頼できる不動産会社に相談し、慎重に判断しましょう。
なお、不動産売却の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【プロが教える】不動産売却の流れは7ステップ!手続きに必要な書類もわかりやすく解説!
まとめ

本記事では、家を貸すメリット・デメリットや家を貸す場合の契約方法や管理方法をご紹介しました。
使わない家を貸す場合、家の所有権を維持しながら、家賃収入が得られたり、家の劣化を防げたりします。しかし、空室リスクや入居者とのトラブル、管理業務の負担といった手続きもあるため、慎重な判断が必要です。
また、契約方法には、更新可能な「普通借家契約」と契約期間が決められた「定期借家契約」があります。さらに、管理方法も自主管理、不動産会社への委託、サブリースと選択肢があり、状況に応じた管理方法の選択が大切です。
委託やサブリースの場合、不動産会社によってサービスの質に差があるため、実績や対応力を十分に確認して、信頼できる会社を選びましょう。
なお、「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから