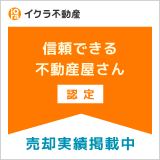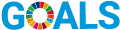Blog
ブログ
2025.10.17
遺品整理は四十九日前がおすすめ?この時期の3つのメリットと手順を詳しくご紹介!

大切なご家族を亡くされた直後、心身ともに大変な状況の中で「遺品整理をいつから始めれば良いのだろうか」と悩まれる方は少なくありません。遺品整理を行う時期に法的な決まりはありませんが、故人の魂があの世へ旅立つとされる四十九日法要までに始めるのが一般的とされています。
なぜ四十九日前が推奨されるのか、どのようなメリットがあるのかを理解しておくと、心の整理をつけながら、相続手続きなども円滑に進められるでしょう。本記事では、四十九日前に遺品整理を行うメリットや、自分で遺品整理の作業を進める具体的な手順、業者に依頼する際の注意点について解説します。

遺品整理を四十九日の前に行う3つのメリット

遺品整理を四十九日前に進めると、精神的な面と実務的な面の両方で多くの利点があります。この期間に整理を開始するメリットを3つお伝えします。
1.遺族の気持ちの整理がつけやすい
大切な人を亡くした直後は悲しみに暮れ、なかなか立ち直れないものです。遺品整理を四十九日前の忌中に少しずつ行うと、故人の持ち物と向き合い、思い出を振り返る時間を意識的に作れます。
整理作業を通じて、故人がいなくなった現実を徐々に受け入れ、心の整理をつけるきっかけにもなるでしょう。また、仏教では故人の魂が現世をさまよっているとされるのが四十九日までの期間です。
四十九日前までに遺品整理を済ませておくと、故人の心残りを断ち切り、安らかに旅立ってほしいという願いが込められます。悲しみを乗り越え、前向きな気持ちで新たな生活を始めるための一助になるでしょう。
なお、遺品整理の最適な時期については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:遺品整理の最適な時期はいつ?後悔しないための3つのタイミングをご紹介! | ビリーフ株式会社
2.経済的な負担を軽減できる
遺品整理を早めに始めると、経済的な負担を軽減できるメリットがあります。故人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品整理が終わるまでは賃貸契約が継続し、家賃や管理費を払い続けなくてはなりません。
四十九日前に整理を完了し、退去手続きを進めると、これらの費用を削減できます。さらに、クレジットカードやサブスクリプションサービスなどの契約内容を確認し、早期に停止・解約すると、思わぬ出費を防げる場合があります。
また、相続に必要な重要書類(戸籍謄本、預金通帳など)を早期に発見できる可能性も高まり、期限のある各種手続きのスムーズな着手につながるでしょう。
3.形見分けや遺産の相続に関する相談がしやすい
四十九日法要は、親族が一堂に会する貴重な機会です。法要に合わせて遺品整理を四十九日前に済ませておくと、親族が集まった場で形見分けや遺産の相続に関する相談を効率的に行えます。
特に、遠方に住む親族がいる場合、改めてスケジュールを調整する手間が省けるでしょう。法要のタイミングで遺品の確認を行えば、時間が経ってから親族間のトラブルが起こるリスクを未然に防ぎ、公平で誰もが納得のいく形で整理を進められます。
故人の思い出を共有し、家族の絆を深める貴重な機会にもなります。
自分で遺品整理を49日前に進める3つの手順
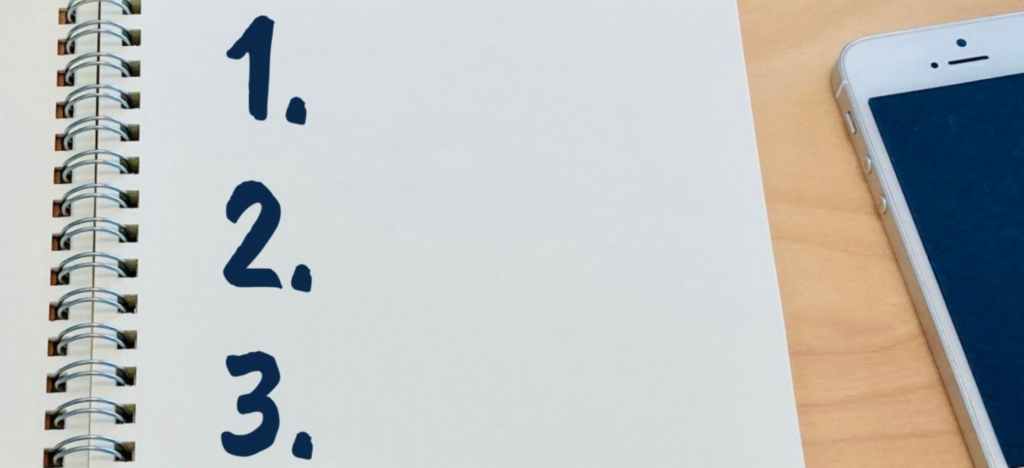
自分で遺品整理を四十九日前に完了させるには、計画的かつ慎重に進めなければなりません。故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、必要な作業を効率よく進める手順について解説します。
1.親族間で遺品整理の方針と時期を決定する
遺品整理は財産に関わるため、独断で進めるのではなく、必ず親族全員の許可と合意を得てから始めるのがトラブル回避の第一歩です。まず、誰が遺品整理の主体となるのか、いつまでに作業を完了させるのかといった大まかなスケジュールを決定しましょう。
四十九日法要に合わせて形見分けを行うのを目標にすると、作業にメリハリが生まれます。また、故人の遺言書やエンディングノートの有無を確認し、もしあればその内容を尊重して整理を進めるのが大切です。
相続人の間で作業の進め方について共通認識を持つと、後の作業をスムーズに進められます。
2.遺品を「貴重品」「形見分け」「処分」の3つに分別する
遺品整理の最も重要なステップは、遺品の分別です。感情的になりやすい時期ですが、残すものと処分するものの判断を客観的に行うのが大切です。
以下の3つの基準で分類を行い、迷うものはすぐに決めず、一時保管するスペースを設けて時間を置いてから再検討するようにしましょう。
|
分類 |
概要 |
具体的な品目 |
|
貴重品(重要書類) |
相続や各種手続きに必須となるため、優先して探す |
現金、預金通帳、有価証券、不動産の権利書、生命保険証書、年金手帳、実印、遺言書、デジタル遺品のパスワードなど |
|
形見分け |
遺族や親族が故人の思い出として引き継ぎたいもの |
衣類、装飾品、写真、手紙、思い出の品など |
|
処分・供養 |
誰も引き取らず、廃棄や供養が必要なもの |
不用品、古い家電製品、家具、大量の衣類など |
分別作業は、重要書類を見落とさないよう慎重に進める必要があります。
3.不用品の処分と貴重品の管理をする
分別が終わったら、次のステップとして不用品の処分と貴重品の管理に移ります。処分する不用品は、自治体のごみ出しルールに従って廃棄するか、遺品整理業者や不用品回収業者に依頼して引き取ってもらいましょう。
大型家具や家電の処分は時間と手間がかかるため、四十九日法要までの日程を考慮して早めに手配してください。一方、貴重品や重要書類は、紛失や盗難を防ぐために、相続人が責任をもって厳重に保管し、相続手続きに必要な情報を整理しておきます。
また、デジタル遺品(スマートフォンやPCのデータ、ネットサービス)についても、解約やデータの消去を四十九日までに進めるのが望ましいでしょう。
遺品整理の専門業者を選ぶ際の3つの注意点

遺品整理を四十九日前に自力で完了させるのが難しい場合や、遠方に住んでいる、仕事が忙しいといった人は、遺品整理業者への依頼を検討しましょう。信頼できる業者を選ぶポイントを3つお伝えします。
1.見積もり内容の詳細と追加料金の有無を確認する
業者を選ぶ際は、必ず複数の業者から相見積もりを取り、料金体系を比較しましょう。見積もり書に作業費、運搬費、処分費などが明細として詳細に記載されているかを確認してください。
特に、追加料金が発生する可能性がある項目(例:作業途中で発見された貴重品の仕分け、特殊清掃の有無など)について、事前に明確な説明を受け、書面で確認するのが重要です。遺品整理の経験が豊富で、故人の家に合わせた適切な提案をしてくれる業者を選ぶと、費用面での安心につながります。
2.遺品整理士の資格と実績を確認する
遺品整理は、故人の思い出が詰まった品物を扱うため、単なる不用品回収とは異なり、遺族の気持ちに寄り添った対応が求められます。信頼できる業者を見極めるための一つの目安として、遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているか、また作業実績が豊富にあるかを確認しましょう。
遺品整理士は、遺品整理に関する専門知識と法的な知識を学んでおり、適切な手順で作業を進めてくれます。公式サイトや口コミで、故人や遺族への配慮ある対応を実践しているか、実績を確認するのが大切です。
なお、失敗しない遺品整理業者の選び方については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
関連記事:失敗しない遺品整理業者の選び方は?チェックすべき8つのポイントをご紹介! | ビリーフ株式会社
3.遺品の供養や買取サービスの有無を確認する
遺品には、処分に抵抗があるもの、供養したいもの、また価値があり買取可能なものが含まれている場合があるでしょう。そうした品物に対応するため、遺品整理業者によっては、合同供養や提携寺院での供養、あるいは骨董品・貴金属・ブランド品などの買取サービスを提供しています。
買取が成立した場合、遺品整理費用からその金額を差し引くサービスもあるのです。これらのサービスの有無や内容について、事前に確認し、自身のニーズに合った業者を選ぶと、より満足度の高い遺品整理につながるでしょう。
「遺品整理は四十九日前がおすすめ」でよくある3つの質問
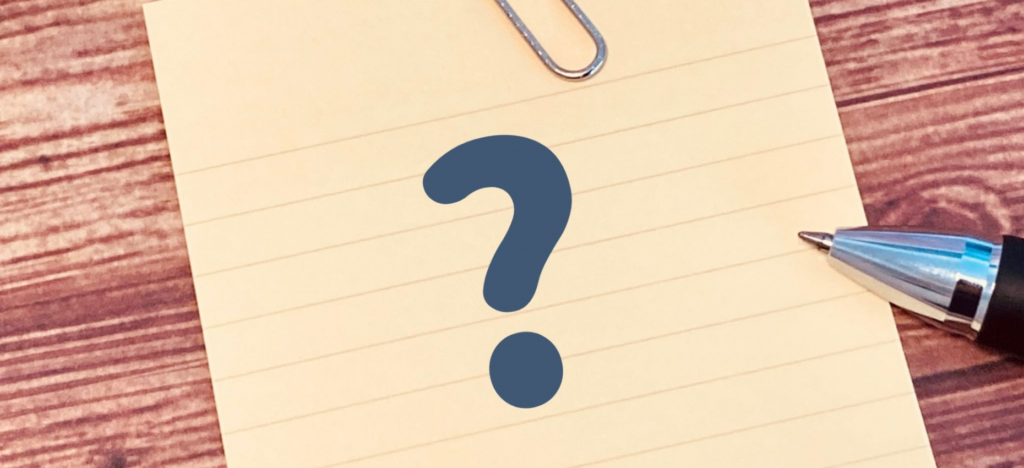
「遺品整理は四十九日の法要前にするべきか」についてよくある質問を3つ紹介します。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
質問1.遺品整理を四十九日を過ぎてから行っても問題ありませんか?
遺品整理の時期に法的な期限はないため、四十九日を過ぎてから行っても問題ありません。四十九日という期間は、仏教における故人の魂が旅立つとされる一つの区切りです。
それまでに遺品整理を済ませるのが望ましいのは、心の整理や手続きの円滑化といった実務的なメリットがあるためです。しかし、気持ちの整理がついていない場合や、親族の都合で集まれない場合などは、無理に四十九日までに終わらせる必要はありません。
ただし、相続税の申告期限(死後10ヶ月以内)や、故人が賃貸物件に住んでいた場合の退去期限など、実務的な期限があるものには注意が必要です。
質問2.遺品整理を始める前に、必ずやっておくべきことはありますか?
整理を始める前に、親族間で遺品整理の方針について合意を得るのが大切です。貴重品や重要書類が遺品に含まれている可能性があるため、作業を始める前に、遺言書の有無や相続人の確認を行い、トラブルを防ぐための共通認識を持っておきましょう。
また、遺品整理の範囲、形見分けのルール、費用の負担についても話し合い、書面などで記録を残しておくと安心です。遺品整理業者に依頼する場合は、この段階で相見積もりを始めるのが効率的です。
質問3.遺品整理で出た不用品やゴミの処分方法には、どのようなものがありますか?
遺品整理の作業で最も手間がかかるのが、大量に出た不用品やゴミの処分です。主な処分方法としては、自治体のルールに従った一般ゴミとしての廃棄、大型家具や家電の粗大ゴミとしての回収依頼、リサイクルショップやフリマアプリでの売却、遺品整理業者や不用品回収業者への依頼などが挙げられます。
手間をかけずに一括で処分したい場合は、遺品整理業者に依頼するのが最も効率的です。まだ使えるものや価値があるものは、寄付や買取を検討すると、費用を抑えつつ遺品の有効活用にもつながります。
まとめ

遺品整理は、故人を偲び、遺族の心の整理をつける大切なプロセスです。四十九日前に始めると、経済的な負担の軽減や形見分けのスムーズな進行、故人が安心して旅立つための準備という意味で、メリットがあります。
遺品整理を四十九日前に進める際は、まず親族間で方針を合意し、貴重品、形見分け、処分の3つに遺品を分別するところから始めましょう。もし個人での作業が難しい場合は、信頼できる遺品整理業者の専門知識とサポートを借りるのも一つの選択肢です。
本記事で紹介した手順と注意点を参考に、後悔のない遺品整理を進めてください。