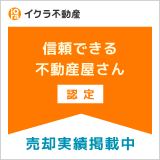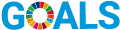Blog
ブログ
2025.09.13
遺品整理とは?一般的な手順や事前に確認すべき重要事項をご紹介!
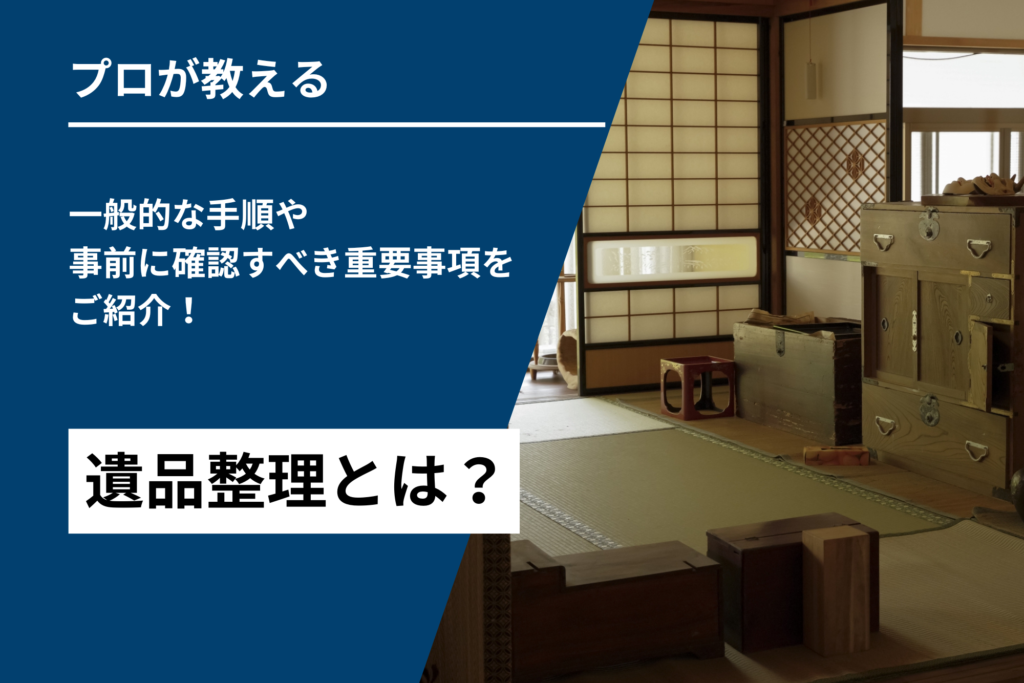
遺品整理とは、故人が所有していた品物を整理する作業です。しかし、故人が残した品々をどうすれば良いのか分からず、何から手をつければいいのか途方に暮れてしまう方も少なくありません。
本記事では、遺品整理の定義から始めるタイミング、具体的な手順など、知っておきたい情報を網羅的に解説します。遺品整理は、故人との別れに向き合い、気持ちを整理するための大切な一歩です。
ぜひ最後まで読み、安心できる一歩を踏み出す参考にしてください。

遺品整理とは?

遺品整理の作業を始める前に、まずは本質的な意味を理解しておくのが大切です。ここでは、遺品整理の目的や、よく似た言葉である生前整理や形見分けとの違いについて解説します。
遺品整理の主な目的
遺品整理とは、故人が所有していた品物を整理する作業です。単に故人の部屋を片付けて不用品を処分するだけでなく、故人が残した貴重品や重要書類、思い出の品などを仕分けし、形見として残すものや相続の手続きに用いるものを明確にする目的があります。
作業を通じて、遺族は故人が歩んだ人生に改めて向き合います。遺品整理は、故人との思い出を振り返り、気持ちを整理するための大切な時間です。
生前整理との違い
故人が存命のうちに自身の身の回りのものを整理するのが、生前整理です。遺品整理が故人の死後に遺族が行う作業であるのに対し、生前整理は本人が自分の意思で行います。
自分の持ち物を整理して、万が一のときに残された家族の負担を減らす目的があります。また、何を残し、何を処分するかを自分の意思で決定可能です。
そのため、デジタル遺品の整理や相続の準備なども含め、より主体的に人生の終わりを準備する活動として注目されています。
形見分けとの違い
遺品整理の作業の中で、故人が大切にしていた品や愛用品を、遺族や親しい関係者で分け合うのが、形見分けです。故人の思い出を身近に感じ、偲ぶのを目的として行われます。
遺品整理が故人の持ち物すべてを対象とするのに対し、形見分けは故人の意思や遺族の意向に基づいて、特定の品物だけを対象とします。衣類や時計、装飾品などが一般的に形見分けの対象です。
高価な品物は相続財産となるため、慎重な検討が必要です。
遺品整理をはじめるタイミングは3つ

遺品整理にいつから取り組むべきか、明確な決まりはありません。しかし、適切なタイミングで始めれば、後の手続きがスムーズに進むでしょう。
この章では、遺品整理を始める主な3つのタイミングについて解説します。
1.四十九日を迎えた後
多くの遺族にとって、死後間もない時期は、各種手続きや葬儀の準備などで多忙を極めます。また、精神的にも悲しみが深く、冷静な判断が難しい時期です。
そのため、四十九日の法要を終え、遺族の気持ちが落ち着いてから遺品整理を始めるのが一般的です。四十九日という節目を迎えて、故人との別れに区切りをつけると、心を落ち着かせて作業に臨めるでしょう。
2.相続税の申告期限
遺品に相続財産が含まれている場合、相続税の申告期限を考慮して作業を進める必要があります。相続税の申告・納税期限は、相続の開始(故人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限を過ぎると延滞税が課される可能性があるため、不動産や有価証券、美術品などの貴重品は早めに仕分けし、財産の全体像を把握しておきましょう。
3.賃貸物件の契約期限
故人が賃貸物件に住んでいた場合、速やかに遺品整理を進める必要があります。賃貸物件の契約は、故人が亡くなると同時に解除されるわけではありません。
一般的に、死亡後も契約は継続し、家賃が発生します。契約書の内容にもよりますが、速やかに遺品整理を終えて物件を明け渡すと、余計な費用を抑えられるでしょう。
契約内容を事前に確認し、立ち退き期限を考慮した上で計画を立ててください。
遺品整理で確認すべき重要事項は4つ

遺品整理を始める前に、いくつか注意すべき点があります。親族間でのトラブルを避け、円滑に作業を進めるには、事前の準備が欠かせません。
ここからは、遺品整理で確認すべき4つの注意点について解説します。
1.遺言書やエンディングノートの有無
遺品整理を始める前に、故人が遺言書やエンディングノートを残していないか確認しましょう。遺言書には法的な効力があり、故人の意思に基づいて遺品整理を進めなければなりません。
また、エンディングノートには、遺品整理の進め方や財産に関する情報、親しい人へのメッセージなどが書かれている場合があり、故人の思いを尊重した整理の手助けとなります。
2.相続放棄を検討しているか
故人の財産がマイナス(借金など)である場合、相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄の手続きは、故人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
遺品整理の過程で財産を処分したり使用したりすると、相続を「承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるのです。相続放棄を検討している場合は、遺品整理を始める前に弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
3.親族間での事前の話し合い
遺品整理は、故人との思い出が詰まった品々を扱うため、感情的になりやすく、親族間でのトラブルに発展する可能性があります。形見分けや貴重品の扱いで意見が食い違うケースも珍しくありません。
トラブルを避けるために、作業を始める前に必ず親族全員で話し合いの場を設け、誰が何をするのか、どのような品物をどのように扱うかなど、役割分担や基本的な方針を決めておくのが大切です。
4.廃棄物に関するルールの確認
遺品整理で大量の不用品が出た場合、自治体の定める廃棄物処理ルールに従う必要があります。特に、大型家具や家電製品は粗大ゴミとして特別な手続きが必要な場合があります。
また、故人が賃貸住宅に住んでいた場合、ゴミの搬出経路や時間帯にも注意が必要です。近隣住民に配慮し、騒音トラブルなどを避けるためにも、事前に自治体のルールや賃貸契約の規定を確認しておきましょう。
遺品整理の一般的な手順は3つ
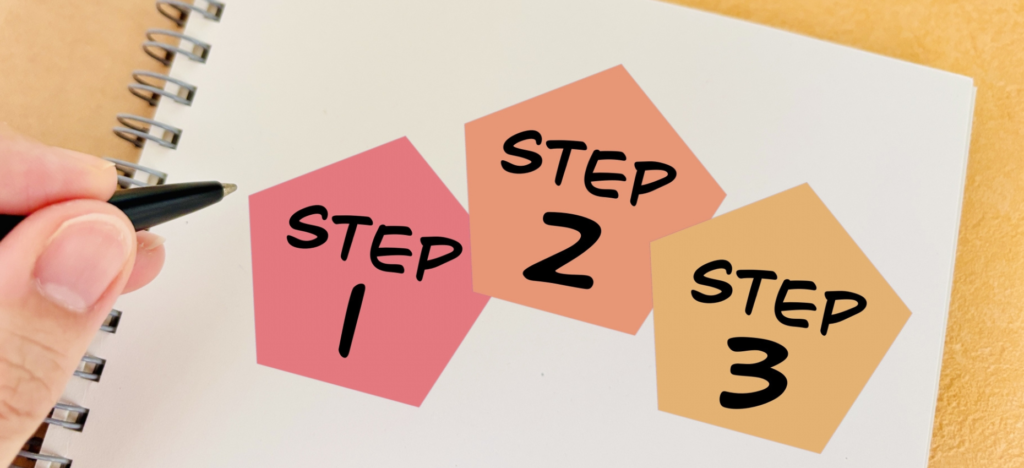
遺品整理をスムーズに進めるためには、手順に沿って作業を進めるのが重要です。遺品整理の一般的な流れを3つのステップに分けて解説します。
ステップ1.遺品の仕分けと分別
遺品を「残すもの」「不要なもの」「迷うもの」の3つに大きく分類します。「残すもの」には、貴重品(現金、通帳、有価証券、貴金属など)、重要書類(権利書、保険証券、契約書など)、形見分けの品、思い出の品(写真、手紙、日記など)です。
「不要なもの」は、明らかなゴミや、劣化して使えないものなどです。「迷うもの」は、故人が大切にしていたが自分では使い道が分からないものや、価値の判断が難しいものなどです。
これらは一度保留にしておき、後日改めて判断しましょう。
ステップ2.遺品の処分方法を検討
仕分けが終わったら、不要なものを処分します。処分方法は多岐にわたります。日常的なゴミや小型の不用品は、自治体のルールに従って分別し、ゴミ収集に出しましょう。
また、まだ使える家具や家電、衣類などは、リサイクルショップやフリマアプリなどを利用して売却する方法があります。遺品整理業者や不用品回収業者に依頼すれば、大型家具や大量のゴミをまとめて引き取ってもらうことも可能です。
ステップ3.清掃と原状回復
遺品の搬出がすべて終わったら、最後に部屋の清掃を行います。賃貸物件の場合は、契約時の状態に戻す原状回復も必要です。ハウスクリーニングの専門業者に依頼すると、より短時間で清潔な状態に戻せます。
長期間空き家になっていた場合は、特殊な清掃が必要なケースもあるため、専門業者に相談するのがおすすめです。
なお、ハウスクリーニングの料金相場については、こちらの記事でご紹介しています。
関連記事:ハウスクリーニングの料金相場は?料金を左右する条件や安くするコツをご紹介! | ビリーフ株式会社
遺品整理とはでよくある3つの質問

遺品整理とはでよくある質問を3つ紹介します。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
質問1.遺品整理は業者に依頼するべきですか?
遺品整理業者に依頼する最大のメリットは、遺族の精神的・身体的負担を軽減できる点です。遺品整理は多大な時間と労力を要する作業であり、精神的に辛い時期に行うのは大きな負担となります。
業者に依頼すると、仕分けから搬出、清掃までを一貫して任せられるため、作業にかかる時間を大幅に短縮できます。ただし、費用がかかる点や、信頼できる業者を選ぶ必要がある点には注意が必要です。
自分で整理する時間がない方や、体力に自信がない方、遠方に住んでいる方などは、プロの力を借りることを検討してみましょう。
質問2.遺品整理の費用相場はどのくらいですか?
遺品整理の費用は、作業を行う部屋の広さや物の量、作業員の人数、特殊な作業(消臭やハウスクリーニングなど)の有無によって大きく変動します。一般的に、1K〜1DKで数万円、2DK〜2LDKで10万円〜30万円程度が目安です。
ただし、これはあくまで目安であり、故人の持ち物の量や作業環境(エレベーターの有無など)によって費用は上下します。正確な費用を知るには、複数の業者から相見積もりを取り、作業内容や料金の内訳を事前に確認しましょう。
質問3.遺品整理で出てきた不用品はどうすればいいですか?
遺品整理で出てきた不用品は、故人との思い出が詰まった大切な品物と、処分しても差し支えないものに分けられます。まず、家具や家電などまだ使えるものは、リサイクルショップやフリマアプリを利用して売却したり、寄付したりするのが選択肢の一つです。
価値があるものは、遺品買取サービスを利用するのも良いでしょう。故人が愛用していた衣類や小物などは、形見分けとして親しい方々に譲ると、故人を身近に感じてもらえます。
また、大量の不用品や大型ゴミは、自治体のルールに従って粗大ゴミとして出すか、専門の業者に回収を依頼するのが一般的です。
まとめ

遺品整理は、故人を偲び、気持ちを整理するための大切な儀式です。単なる片付けではなく、故人が残した貴重品や思い出の品を一つひとつ丁寧に扱い、次のステップに進むための準備でもあります。
遺品整理を成功させるためには、事前の準備が不可欠です。本記事で紹介した遺品整理の一般的な3つの手順を参考に、まずは遺言書の有無や親族との話し合いから始めてみましょう。
また、時間や労力が足りない場合は、専門の遺品整理業者に相談するのも有効な手段の一つです。故人への感謝の気持ちを大切にしながら、自分に合った方法で遺品整理を進めていきましょう。