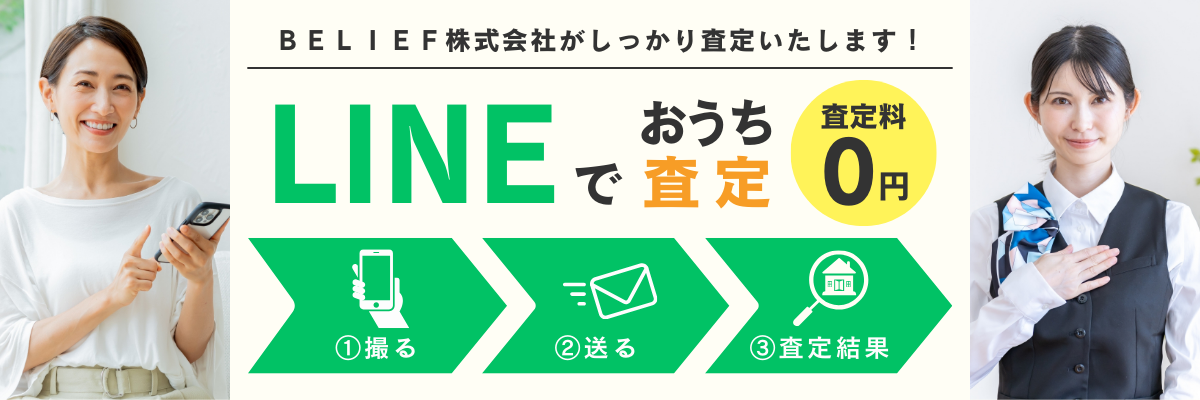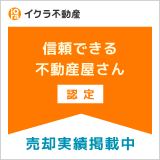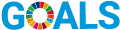Blog
ブログ
2025.05.03
立ち退き料の相場とは?必要なケースや計算方法、安くするコツまで詳しくご紹介!
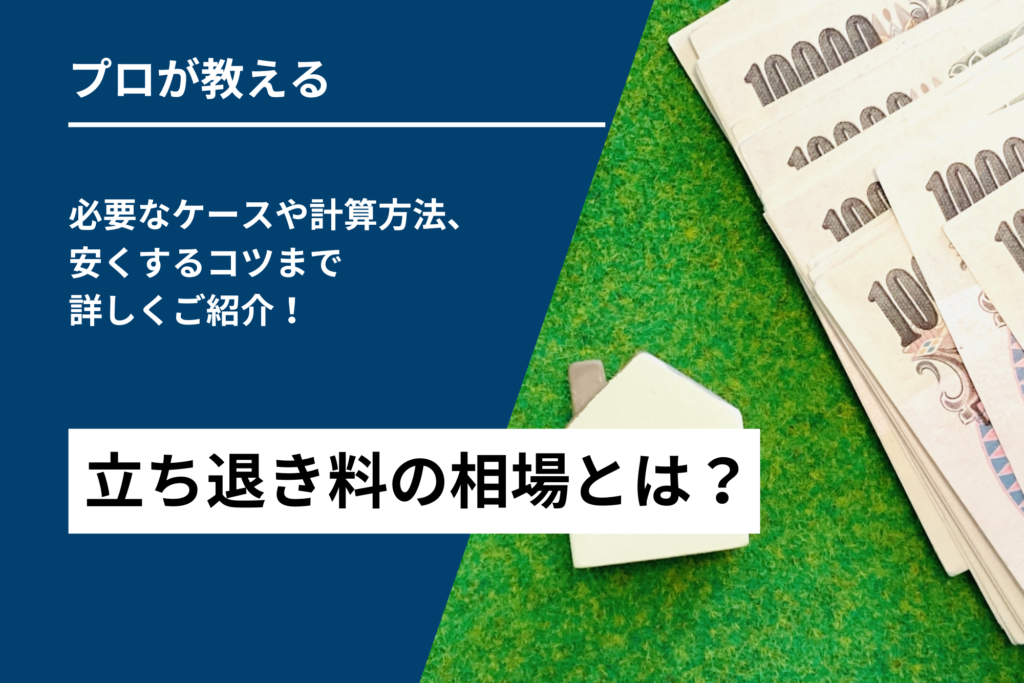
不動産オーナーが建物の建て替えや売却を検討する際に避けて通れないのが立退料の問題です。一体いくら支払うべきなのか、相場はどのくらいなのか、多くの方が頭を悩ませています。
本記事では、立退料が発生する理由から具体的な相場金額から、立退料を抑えるためのコツまで、専門家の視点で徹底解説します。適正な立退料の相場を知り、円滑な交渉につなげましょう。

立ち退き料の相場とは?

立ち退き料は、賃貸住宅の家賃や引っ越しにかかる実費、契約関連の費用などをもとに算出されます。一般的には家賃の半年から1年分が目安とされており、例えば月額8万円の物件であれば、立ち退き料は約48〜96万円程度です。
また、引っ越し費用や仲介手数料、新居の家賃差額なども加味されます。営業店舗の場合は、休業補償などが必要となるため、金額は住宅よりも高くなる傾向です。
建て替えが絡む場合は、建築会社へ相談しましょう。
立ち退き料が生じる理由
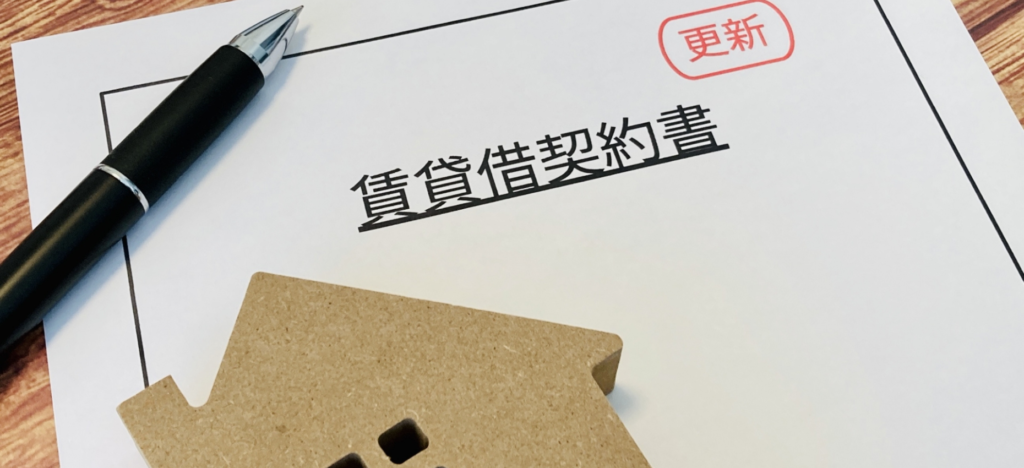
立ち退き料が生じる理由を、以下の2つのポイントから解説します。
- 法的根拠
- 正当事由
立ち退き料の法的根拠
立ち退き料の根拠は、借地借家法第28条に基づいています。この条文では、賃貸人が賃借人に対して契約更新を拒否したり解約を申し入れたりする際「正当事由」が必要とされるのです。
ここでの「正当事由」には、当事者の事情に加え、財産上の給付、すなわち立ち退き料の提示も含まれます。法律上は支払い義務があるわけではありませんが、実務上はこの給付が立ち退き請求の妥当性を補強するために重要視されており、交渉を円滑に進める手段として用いられているのです。
正当事由と立ち退き料の関係
立ち退き料の額は、「正当事由」の強さによって大きく左右されます。貸主側の事情が明確かつ切実であるほど、正当事由が強いとされ、支払う立ち退き料は比較的少額で済むのが一般的です。
例えば、貸主が他に住む家を持っておらず、自身でその建物を使用する必要がある場合は、強い正当事由があるとみなされます。一方で、老朽化や売却など、貸主の都合だけでは正当事由としては不十分な場合も多く、その場合は立ち退き料を多めに提示する必要が生じるでしょう。
立ち退き料が必要になる主なケースは3つ

立ち退き料が必要になるケースはさまざまですが、特に多いのが以下の3つです。
- 大家都合で退去を求める場合
- マンションや店舗を建て替える場合
- 土地の再開発による立ち退きの場合
それぞれの状況によって立退料の相場や交渉方法も異なってきます。立退き料の発生要因を理解すれば、より適切な対応や準備が可能になります。
1.大家都合で退去を求める場合
貸主が自ら建物を使用するために賃借人に退去を求める場合、立ち退き料の支払いが必要とされるのが一般的です。例えば、転勤などで一時的に貸し出していた住宅を、再び自己使用する状況などが該当します。
借主がその物件で生活基盤を築いている場合、移転に伴う負担を考慮し、立ち退き料の支払いが求められます。ただし、借主がほとんど使用していない場合などは、支払い義務が発生しない可能性もあるでしょう。
状況に応じた判断が必要です。
関連記事:売却で不動産会社を比較する際のポイントは5つ|選ぶ際の注意点も詳しく解説します! | ビリーフ株式会社
2.マンションや店舗を建て替える場合
賃貸物件の建て替えを理由に入居者へ立ち退きを求める場合、基本的には立ち退き料の支払いが必要とされます。建物の老朽化や耐震性の問題があったとしても、入居者にとっては生活の場を移す負担があるためです。
たとえ管理者やオーナーにとって合理的な理由があっても、正当な事由として認められるには立ち退き料の提示が重要な要素となります。特に危険が差し迫っていない限り、補償を前提とした対応が求められます。
関連記事:マンション買い替えのタイミングやきっかけは?おすすめのタイミングや買い替えの流れをご紹介! | ビリーフ株式会社
3.土地の再開発による立ち退きの場合
再開発や都市整備などの計画によって賃貸建物の取り壊しが行われる場合、入居者に対して立ち退きを求めるには立ち退き料の支払いが伴うのが一般的です。こうしたケースでは、行政主導で進む場合が多く、移転先の確保や生活再建の負担が大きいため、通常の立ち退きよりも高額な補償が行われる傾向にあります。
賃借人の生活基盤への影響が大きいため、十分な配慮と補償が必要とされます。
立ち退き料が不要なケース

立ち退き料は通常、賃貸人が賃借人に退去を求める際に支払われますが、すべてのケースで必要になるわけではありません。例えば、賃借人が家賃を滞納したり無断で転貸したりするなど契約違反がある場合、契約解除により明け渡しを請求でき、立ち退き料は不要です。
また、定期建物賃貸借契約や契約当初から期限が明示されていた場合も、期間満了による終了のため補償は求められません。さらに、建物に深刻な危険がある場合も例外的に立ち退き料が発生しないケースがあります。
立ち退き料を構成する要素は3つ
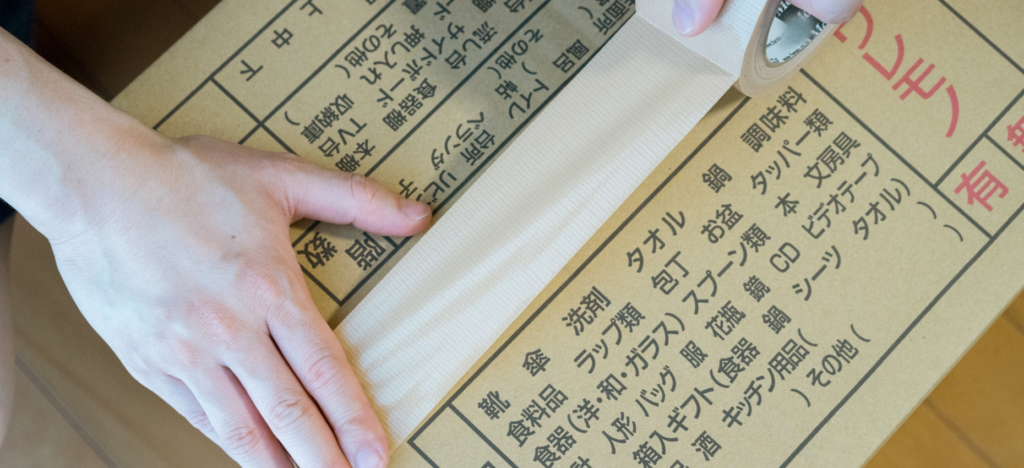
立ち退き料は単なる「退去のための支払い」ではなく、複数の要素から構成される補償金です。大家側が借主に支払う立ち退き料には、主に以下の3つの要素が含まれています。
- 移転費用の補償
- 利用権の補償
- 利益の補償
1.移転費用の補償
立ち退き料には、借主が新たな住居へ移る際に必要となる実費の補償が含まれます。具体的には、引っ越し代や荷物の梱包・運搬費、各種保険、家具の分解や再設置費用、さらに住所変更や移転通知にかかる費用などです。
また、新しい住まいを見つけるための仲介手数料や、敷金・礼金の差額、家賃が上がる場合の増額分も補償の対象となるケースが多く、これらはすべて貸主の都合による退去で必要とされる最低限の補償とされています。
2.利用権の補償(借家権)
借家人が持つ借家権とは、単なる物理的な使用権だけでなく、長年住み慣れた環境や住み心地といった生活の質にも関わる権利です。立ち退きによってこのような非財産的な価値が失われるため、補償の対象となる場合があります。
ただし、借家権そのものの価値を明確に金額で評価するのは難しく、一般的には引っ越し費用などの移転費用の補償に含めて処理されます。地域や事例によっては、個別に評価される場合もあるでしょう。
3.利益の補償(営業補償)
店舗の立ち退きに際しては、移転による損失を補うために「営業補償」が必要です。これは、立地の変化によって売上が減少したり、顧客が離れたりして営業利益に大きな影響が出るためです。
さらに、移転に伴う一時的な休業による収益の喪失や、固定費の継続的な支出、新たな人員確保にかかる費用など、住宅とは異なる特有の不利益が生じます。そのため、営業を行っている店舗では、立ち退き料が高額になるケースが多いのが通例です。
戸建てやアパートの立ち退き料の計算方法は4つ

借家人に立ち退いてもらう際、適正な立退料を算出するのは交渉の成功に不可欠です。紹介する4つの計算方法は、実務で広く活用されています。
それぞれの方法には特徴があり、計算の根拠として裁判所でも認められているものです。立退交渉を円滑に進めるためにも、これらの計算方法を理解しておきましょう。
1.収益還元方式(差額賃料還元方式)
収益還元方式とは、立ち退きにより発生する家賃の増加分を基に立ち退き料を算出する方法です。この手法では、現在の家賃と移転先の家賃との差額に複利年金原価率を掛けて借家権の価値を導き出します。
差額が大きいほど補償額も高くなるのが特徴で、1〜2年分の差額を現在価値として計算するのが一般的です。こうした特徴から、収益還元方式は「差額賃料還元方式」とも呼ばれ、実務でもよく用いられています。
2.割合方式
割合方式は、土地や建物の資産価値に基づき、借主の利用権を数値化して立ち退き料を算出する方法です。具体的には、土地価格に借地権割合と借家権割合を掛けた金額に、建物価格に借家権割合を掛けた金額を加えて求めます。
この方式では、相続税路線価を基にした割合が用いられるケースが多く、不動産の評価を反映した立ち退き料の算出が可能です。物件の資産的価値を考慮した補償が求められる場面で活用されています。
3.収益価格控除方式
収益価格控除方式は、貸主がその物件を自ら使用する場合と、借主に賃貸している場合とで生じる価格差に着目して立ち退き料を算出する手法です。具体的には「自用時の土地建物の価格」から「借家としての価格」を差し引いた金額が借家権として評価されます。
賃貸により資産価値が下がるケースでは、この差額が大きくなるため、立ち退き料の算定において有効な方法とされます。不動産の実勢価値の変化を反映する算出法です。
4.比準方式
比準方式は、過去の借家権取引事例を基に立ち退き料を算出する考え方で、取引価格に各種要因を加味して補正する手法です。算式は「借家権の事例価格 × 事例との要因比較」で表されます。
ただし、借家権は借地権と違って実際の市場で売買されるケースがほとんどないため、具体的なデータに乏しいのが現状です。そのため、この方式は実務上あまり用いられず、理論的・参考的な位置づけとして扱われるケースが多くなっています。
立ち退き料を安くするコツは7つ

建物オーナーにとって、立ち退き料は大きな負担となります。しかし、適切な交渉戦略を取れば、合理的な範囲内に抑えることも可能です。
ここからは、立退料を抑える7つの方法を紹介します。これらの方法は法的に問題なく、かつ借主との良好な関係を維持しながら進められる実践的なアプローチです。
1.空室が多くなり次第着手する
立ち退きは、入居者が減ってから計画的に進めるのが一般的です。建て替えを視野に入れる場合は、まず新規の入居募集を停止し、空室の割合が高まった段階で交渉を開始すると、手間や費用を抑えられるでしょう。
特に店舗付き物件では、テナントが自発的に退去したタイミングが好機となります。店舗の立ち退きは交渉や補償が複雑になるため、自然退去後に建て替え計画を立てるのが現実的な進め方です。
2.代替物件を提供する
立ち退きに際して、金銭の支払い以外に代替物件を提供する方法も「財産上の給付」として認められています。借地借家法では、給付の形式を金銭に限っておらず、貸主が所有する他の物件を入居者に優先的に提供するのも有効な手段です。
例えば、取り壊し予定の建物近隣に別のアパートを所有している場合、その物件に移転先として入居してもらう方法で、立ち退き料の負担を軽減できます。
3.定期借家契約への切り替えを交渉する
立ち退き料の負担を抑える方法の一つに、定期借家契約への切り替えがあります。定期借家契約は更新がなく、契約期間満了と同時に確実に契約が終了するため、立ち退き料を支払わずに物件を明け渡してもらえる可能性があるのです。
ただし、住宅で2000年3月1日以前に締結された普通借家契約は、定期借家契約へ変更できない点に注意が必要です。店舗や事務所などの契約であれば、時期を問わず切り替えが可能とされます。
4.原状回復を免除する
立ち退き交渉の際に、借主の原状回復義務を免除する方法で立ち退き料の削減が期待できます。通常、借主は退去時に物件を元の状態に戻す義務がありますが、建て替えを予定している物件では原状回復が不要となるケースもあります。
特に店舗物件では、内装撤去などに多額の費用がかかるため、原状回復の免除は借主にとって大きなメリットとなり、交渉を円滑に進める有効な手段となるでしょう。
5.用法違反等の解除事由がないか確認する
立ち退きを検討する際は、借主に用法違反などの解除事由がないかを事前に確認しておくのが重要です。例えば、ペット禁止の物件で動物を飼っていたり、住居専用として契約している物件を無断で店舗利用していたりした場合は、契約違反に該当する可能性があります。
こうした場合、信頼関係が破綻していれば契約解除が認められ、立ち退き料を支払う必要がない事例もあります。ただし、解除には法的な判断が必要となるため、弁護士への相談が不可欠です。
6.退去までの賃料を免除する
立ち退き料を抑える手段のひとつは、退去までの賃料を免除し、契約を無償の使用貸借に切り替える方法です。使用貸借契約では、借主の権利が普通借家契約よりも弱くなるため、貸主が退去を求めやすくなります。
この方法を取るには、まず現在の賃貸契約を借主と合意の上で解除し、新たに使用貸借契約を結ぶ必要があります。賃料の免除を提案すれば、借主にとっても負担軽減となり、交渉がスムーズに進む可能性があるでしょう。
7.敷金を事前に返金する
立ち退き交渉を円滑に進める手段として、敷金の前倒し返金が有効です。敷金は本来、家賃滞納や原状回復費用に備えて預かるものですが、立ち退きが前提となる物件ではその役割が薄れるため、早期に返金する方法で借主の資金負担を軽減できます。
特に店舗物件では高額な敷金を預けているケースが多く、返金によって資金繰りが改善されれば、立ち退き要求に対する借主の反応も柔軟になりやすく、結果的に立ち退き料を抑える効果が期待できます。
不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

「ビリーフ株式会社」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。
さらに、不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、実務経験を活かして信頼性の高いアドバイスを提供しています。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから
立退料の相場でよくある3つの質問
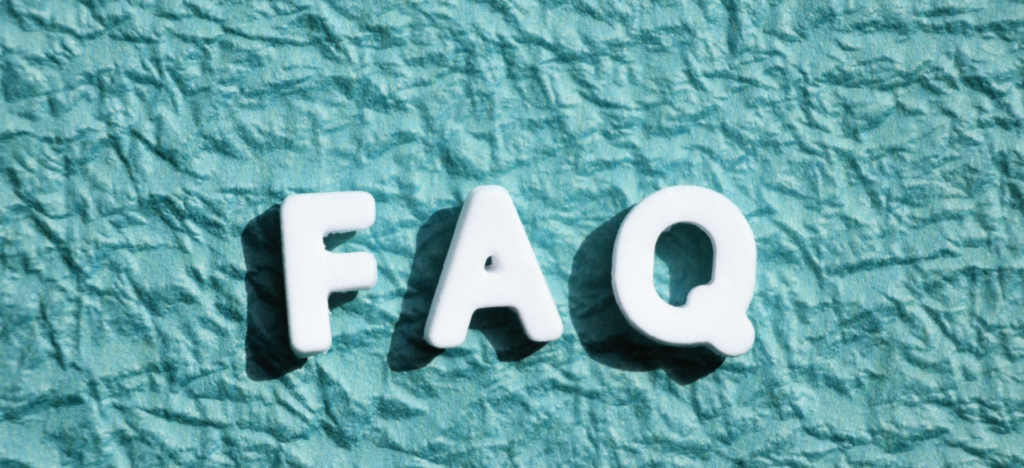
不動産オーナーや借主の方から、立退料に関する質問を多く頂きます。ここからは、立退料に関して特に頻繁に寄せられる3つの質問について、専門的な知見をもとに解説しましょう。
質問1.立ち退き料を支払うタイミングは?
立ち退き料は通常、物件が明け渡されたタイミングで支払われます。先に全額を支払ってしまうと、退去が実行されないといったリスクがあるため、明け渡し後の支払いが基本です。
ただし、引っ越しに伴う初期費用の負担が借主の障害となるケースもあるため、一部を前払いするなど柔軟に対応するのが有効です。支払時期については、合意書などで明確に取り決めておくと、双方にとって安心した交渉が可能になります。
質問2.立ち退き交渉を行う際のポイントは?
立ち退き交渉では、「相場分を払えば退去してもらえる」という安易な考えは通用しません。交渉は思うように進まない場合が多いため、丁寧かつ粘り強い対応が求められます。
初期段階ではオーナー本人や法的な専門家が対応し、借主の不安や感情に真摯に向き合う姿勢が大切です。相手が退去に応じない理由をしっかり把握し、必要であれば支援先の紹介も視野に入れましょう。
対立が深まった場合は無理に交渉を続けず、弁護士などの専門家に任せる判断も重要です。
質問3.立ち退き料に消費税はかかる?
立ち退き料には、原則として消費税は課税されません。消費税がかかるのは「役務の提供」や「資産の譲渡」といった対価性のある取引に限られますが、立ち退き料はこれらには該当せず、あくまで損害補填や契約終了に伴う補償金といった性質を持ちます。
そのため、課税対象外として扱われます。金銭のやり取りが発生しても、取引行為とみなされない以上、消費税の心配は不要といえるでしょう。
まとめ

立ち退き料の相場は賃貸住宅では40〜80万円程度、店舗では業種によって数百万円から億単位まで幅広く設定されています。立ち退き料が発生する理由は借地借家法に基づくもので、正当事由が弱いほど高額になる傾向です。
立ち退き交渉は専門的な知識が必要なため、建て替えを検討する場合は実績のある建築会社や不動産専門家への相談をお勧めします。
なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから