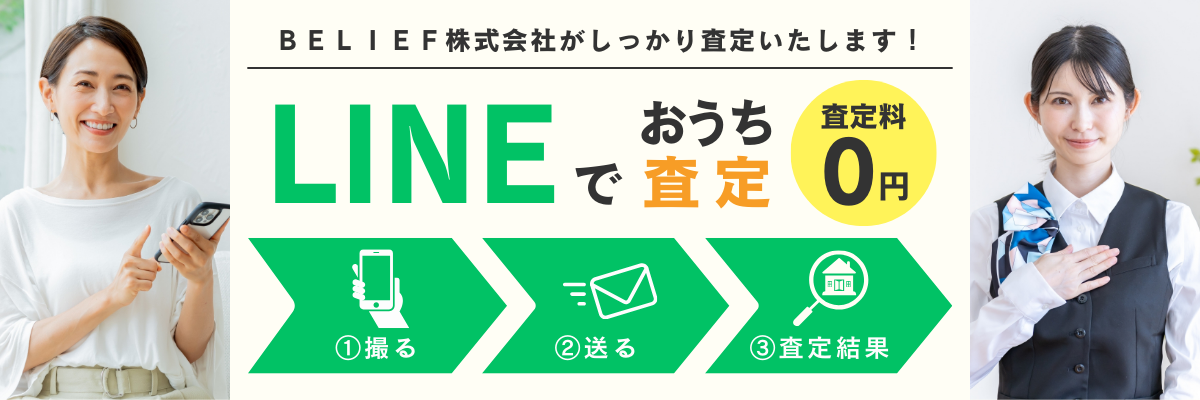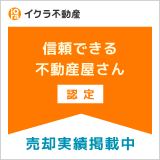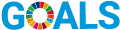Blog
ブログ
2025.03.04
家の耐用年数とは?物件種別で見る耐用年数の違いや寿命が近づいた家を手放す方法をご紹介!
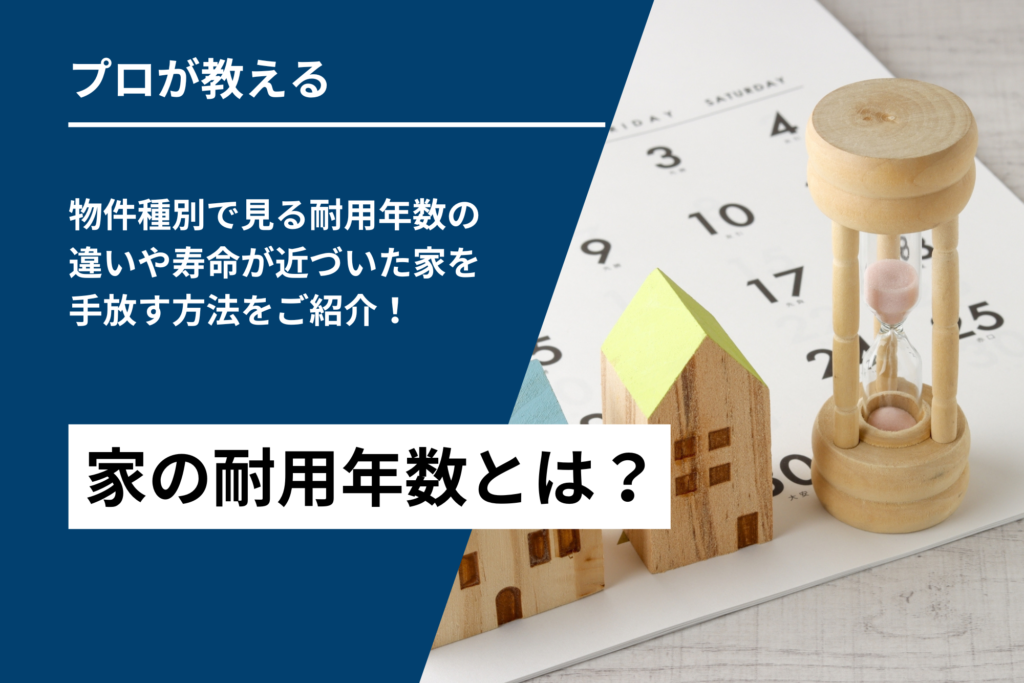
「家の耐用年数を超える前に売却するか、修繕するか」で、悩まれている方もおられるのではないでしょうか。建物の種類によって耐用年数は異なりますが、耐用年数を超えても住めないわけではありません。
本記事では、家の耐用年数の概要や物件種別で見る耐用年数の違い、寿命が近づいた家を手放す方法をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

家の耐用年数とは?

まずは、家の耐用年数について解説します。
- 物理的耐用年数
- 法定耐用年数
- 経済的残存耐用年数
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
物理的耐用年数
物理的耐用年数とは、建物や機器が本来の性能を維持しながら使用できる期間です。たとえば、自動車やエアコンなどの製品は、長年使用すると劣化して、本来の性能を発揮しにくくなります。
住宅においても同様で、木造住宅の耐用年数は立地条件や日頃のメンテナンスによって異なります。適切な手入れが施されていれば、耐用年数を超えても十分に住み続けられる場合が多いです。このため、一律に耐用年数を決めるのは難しく、個々の状態に応じた判断が求められます。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、国が定める減価償却の基準となる年数であり、建物の種類や構造によって異なります。たとえば、木造住宅は22年とされていますが、これはあくまで税務上の基準であり、実際の住宅の寿命を示すものではありません。
建物の耐久性は、使用される素材や維持管理の状況によって大きく変わるため、法定耐用年数を超えた住宅でも適切に手入れされていれば十分に利用可能です。このため、法定耐用年数を建物の寿命と同一視するのではなく、資産評価の1つの目安として捉えましょう。
経済的残存耐用年数
経済的残存耐用年数とは、建物が市場価値を維持できる期間です。これは、建物の物理的な耐久性だけでなく、周辺環境や市場の需要、修繕の状況などさまざまな要因によって決まるのが特徴です。
たとえば、築年数が古くても適切なリフォームやメンテナンスが施され、住宅需要が高いエリアにある場合は、価値が長く維持される可能性があります。一方で、建物自体がまだ使用可能でも、需要が低下した地域では早期に価値が下がる場合もあります。
このため、経済的残存耐用年数は一律に決められるものではなく、個別の状況に応じた評価が必要です。
物件種別で見る耐用年数の違い

次に、物件種別で見る耐用年数の違いについて解説します。
- 木造一戸建て
- 木造アパート
- マンション
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
木造一戸建て
木造住宅の耐用年数は、一般的に20年程度とされていますが、これは物理的な寿命を示すものではありません。実際には、適切なメンテナンスや修繕を行えば、50年以上快適に住み続けられます。
また、耐用年数を左右する要因として、施工の品質や立地条件、気候の影響が挙げられます。湿気が多い地域では木材の劣化が早まりやすいため、定期的な点検や防腐対策が大切です。長く住み続けるためには、計画的なリフォームや修繕を行い、住宅の状態を適切に管理する必要があります。
木造アパート
木造アパートの耐用年数は、一般的に20〜22年とされています。一戸建てとは異なり、アパートは複数の住人が入れ替わるため、定期的なメンテナンスや設備交換が欠かせません。水回りは、適切な修繕を行うことで建物の劣化を抑え、耐用年数を延ばせます。
また、湿気の多い環境では、カビや腐食のリスクが高まるため、防水対策や換気の工夫が必要です。このように、適切な管理を行えば、法定耐用年数を超えて長期間にわたり快適に利用できる可能性があります。
マンション
マンションの耐用年数は、一般的に47年とされています。これは、鉄筋コンクリート造が採用されているため、木造住宅に比べて耐久性が高い点が理由の1つです。
さらに、マンションでは個々の住戸だけでなく、エントランスや廊下、エレベーターといった共用部分の定期的な修繕やメンテナンスが実施されています。このため、建物全体の劣化が抑えられ、結果として長期間の使用が可能です。
減価償却の意味と計算方法

次に、減価償却の意味と計算方法について解説します。
- 減価償却の意味
- 計算方法
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
減価償却の意味
減価償却とは、建物や設備などの固定資産の購入費用を、一度に全額経費として計上するのではなく、耐用年数に応じて分割して計上する会計処理です。たとえば、不動産を購入した場合、その価値は時間の経過とともに減少すると考えられるため、一定の割合で毎年費用として計上されます。
減価償却の対象となるのは、取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上ある資産ですが、土地のように経年による価値の減少がないものは対象外です。この処理を適切に行えば、経営状況を正確に把握できます。
なお、不動産の減価償却については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:不動産の減価償却とは?計算方法や注意点、よくある質問まで詳しくご紹介します!
計算方法
不動産を住居用として取得した際の減価償却の計算方法には、主に以下の種類があります。
- 定額法
耐用年数に応じて毎年一定額を減価償却する方法で、資産価値の減少が均等に計上されるため、初年度の利益が比較的多く残る特徴がある。計算式は「取得価格 × 定額法の償却率」で算出される
- 定率法
未償却残高に対して一定の割合で減価償却を行うため、初期の減価償却費が大きく、年々減少していく仕組み。計算式は、「未償却残高 × 定率法の償却率」で算出される
償却率は、国税庁が公表する一覧表で確認できます。また、2007年の法改正により、適用される償却率が変わる点にも注意が必要です。
耐用年数が過ぎた家に長く住み続けるためのポイントは3つ

次に、耐用年数が過ぎた家に長く住み続けるためのポイントについて解説します。
- 定期的なメンテナンスを心がける
- 専門家に点検を依頼する
- 小まめに掃除する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.定期的なメンテナンスを心がける
設備や建材は、見た目が問題なくても、経年劣化が進んでいる場合があり、放置すると修理や交換の必要性が高まります。水回りは、日常的に使用するため劣化が早く、早めの点検と清掃が大切です。
また、外壁や屋根などの外回りは風雨や紫外線の影響を受けやすく、定期的なチェックを行うと、ダメージを最小限に抑えられます。小さな異常を見逃さず、適切なタイミングで修繕すると、住まいの寿命を延ばして、快適な生活環境を維持できます。
2.専門家に点検を依頼する
住宅の基礎や屋根裏、床下などは自分で確認するのが難しく、異常に気づかないまま劣化が進むケースも珍しくありません。このため、専門家による定期点検を受けると、早期に問題が発見され、大掛かりな修繕を避けられます。
点検費用は、内容によって異なりますが、長期的に見れば修理コストの削減につながる可能性があります。築年数が経過した住宅では、詳細な診断を受け、必要なメンテナンスを計画的に進めましょう。
3.小まめに掃除する
日々の掃除は、単なる清掃ではなく、家の異常を早期に発見する機会にもなります。水回りは劣化しやすく、カビや水漏れの兆候を見逃さないよう注意が必要です。
床や壁のよごれをこまめにチェックすると、小さな傷みを発見しやすくなります。また、外壁や屋根も定期的に確認して、ひび割れや雨どいの詰まりがないかを見ておきましょう。日常的な掃除と点検を習慣化すると、住宅の寿命が延び、快適な住環境を維持できます。
寿命が近づいた家を手放したい場合の方法

次に、寿命が近づいた家を手放したい場合の方法について解説します。
- 建て替え
- 売却
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
建て替え
住宅の老朽化が進んでいる場合、大規模なリフォームを行うよりも建て替えを選択したほうが経済的で合理的なケースもあります。建て替えの費用は、一般的に2,000〜3,000万円ほどかかるとされています。
さらに、工事期間中は仮住まいが必要になるため、家賃や引っ越し費用も考慮しなければなりません。また、建て替えのメリットとしては、間取りや設備を自由に設計できたり、新築として行政の検査を受けられたりする点が挙げられます。
しかし、工期が長くなるため、その間の生活計画も十分に検討する必要があります。
売却
現在の住まいに強いこだわりがない場合や、資金面で建て替えやリフォームが難しい場合は、売却を検討するのも選択肢の1つです。売却を進めるには、まず市場価値を把握しなければなりません。
築年数が30年を超えると、建物の価値は大幅に下がる場合が多く、新築時の価格と比べて大幅に安くなる可能性があります。このため、売却前に複数の不動産会社へ査定を依頼し、適正な価格を見極めましょう。
また、最近では中古物件を購入してリノベーションする需要も高まっているため、現状のまま売却するという方法もあります。
不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

参考:ビリーフ株式会社
「ビリーフ」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。
さらに、不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、実務経験を活かして信頼性の高いアドバイスを提供しています。
家の耐用年数でよくある3つの質問

最後に、家の耐用年数でよくある質問について紹介します。
- 質問1.築年数ごとの経年劣化の特徴は?
- 質問2.家で劣化しやすい箇所は?
- 質問3.寿命が近づいた住宅をスムーズに売却する方法は?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.築年数ごとの経年劣化の特徴は?
築年数ごとの経年劣化の特徴は、以下のとおりです。
- 築10年
外壁や屋根のひび割れ、塗装の剥がれ、水回りの設備の老朽化が目立ちはじめる。この段階で適切なメンテナンスを行うと、劣化を防げる
- 築10~20年
配管の劣化や床下の損傷など、見えにくい部分に影響が出てきやすい。この時期には、部分的なリフォームや設備の交換を検討するのが望ましい
- 築20~30年
過去に修繕した部分が再び劣化している可能性があり、家全体の状態を見直す時期に入る。このため、ライフスタイルの変化に合わせて、バリアフリー化や間取り変更を含めた大規模リフォームを検討するのがおすすめ
質問2.家で劣化しやすい箇所は?
家で劣化しやすい箇所は、以下のとおりです。
- 外壁
風雨や紫外線の影響を受けやすく、ひび割れや塗装の剥がれ、チョーキング(白い粉)が発生しやすい。大きなひび割れが発生する前に、早めに塗装をし直すと、劣化を防げる
- 屋根
劣化すると雨漏りの原因になりやすい。年に数回、目視で見える範囲で状態を確認して、必要に応じて修繕を行う
- 床
フローリングはキズやよごれが蓄積しやすく、湿気の多い場所では腐食の可能性がある。こまめな掃除と定期的なワックスがけが劣化防止に役立つ
- 水回り
キッチンや浴室、トイレはよごれやすく、水漏れのリスクもある。定期的な清掃と点検でトラブルを未然に防ぐことが大切になる
質問3.寿命が近づいた住宅をスムーズに売却する方法は?
寿命が近づいた住宅をスムーズに売却する方法は、以下のとおりです。
- 不動産会社に買取依頼をする
住宅を所有しているだけでも維持費や税金がかかるため、早めの売却を検討する。築年数が経過するほど市場価値が下がり、買い手が見つかりにくくなるため、短期間で売却できる不動産業者に買取を依頼するのも1つの方法
- 古屋ありの土地を購入する
最近は中古住宅を購入し、自分好みにリノベーションする人が増えている。このため、古家付きの土地として売却すれば、解体費用をかけずに買い手を見つけやすくなる
- 住宅診断(ホームインスペクション)を実施する
第三者の住宅診断で物件の状態を客観的に示せるため、買い手の安心感にもつながる
なお、不動産売却で信頼できる不動産会社については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【プロが教える】不動産売却はどこがいい?特徴や信頼できる業者選びのポイントを徹底解説!
まとめ

本記事では、家の耐用年数の概要や物件種別で見る耐用年数の違い、寿命が近づいた家を手放す方法をご紹介しました。
家の耐用年数には、物理的耐用年数や法定耐用年数、経済的残存耐用年数の3種類があり、それぞれ異なる耐用年数で建物の寿命を判断します。種類によっても耐用年数は異なり、木造一戸建てやアパートは比較的短く、マンションは耐久性が高い傾向にあるのが特徴です。
また、建物や設備などの固定資産の購入費用は、一度に全額経費として計上するのではなく、耐用年数に応じて分割して計上する減価償却で処理します。耐用年数を超えた家でも、定期的なメンテナンスや専門家による点検を行えば、長く住み続けられます。
さらに、掃除や点検をしておけば、小さな傷みを発見しやすくなるため、定期的なメンテナンスを心がけましょう。しかし、寿命が近づいていると判断した場合は、建て替えや売却を検討するのがおすすめです。
それぞれにメリット、デメリットがあるため、家庭の環境やニーズにあった方法を選んでください。売却する場合は、事前に複数の不動産会社へ査定を依頼し、適正な価格を見極めましょう。
なお、「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。⇒公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから